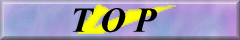act,2
翌日、豹馬は四ッ谷博士にバイクの改造を依頼した。
しかし、簡単に引き受けてはもらえなかった。
当然と言えば当然だが、豹馬は挫けない。
飛行訓練、シュミレーション、地上訓練、戦略会議とどれ一つサボることなく、真面目に参加し、終了と同時に博士に申し出る。 そんな日が何日も続いていた。
今日ですでに十日になる。
「よく続くなぁ」
十三のぼやきともとれる発言にも豹馬は耳を貸さない。
〈コンバトラー〉 の戦闘に関わることだったせいもあるが、これまでバトルチームの要求が通らなかったことなどなかった。
拒絶されたのは今回の件が初めてといってもいい。
「そんだけ豹馬しゃんにとって大切なモノゆうことたい」
大作の言葉に、ちずるが肩をすくめた。
「なんだか妬けちゃうわね」
「じゃあ、僕たちはバイク以下ですか」
納得がいかないというムクレ顔の小介に、三人は呆れたような困ったような表情を浮かべて顔を見合わせた。
これだから子供は …… 。
大人ばかりに囲まれ、子供らしい遊びすら知らずに育った一桁年齢の小介は、大人びた言動が多い。 それ故に他人とのつき合い方や感情の動きに疎いことが気になっていた。
「それとこれとは別よ」
諭すような口調のちずるの言葉を、大作も肯定する。
「そうたい。 別たい」
黙したまま、十三も頷く。
だが三人の眼差しに見下した光はない。 代わりに優しく見守る暖かさがあった。
その思いは小介だけではなく、豹馬に対しても同じだった。
仲間の見守る中、交渉は続く。
なかなか落ちない四ッ谷博士に忍耐を強いられている豹馬に、バトルチームのスケジュール管理を担当する総務部からGPレース観戦チケットが五枚、十三に渡された。
誰の差し金かはわからないが、数週間ぶりの完全休養日だからゆっくり羽根を伸ばして来るように、と言い添えられていた。
「なにか気味が悪いな」
「誰の発案でもえぇやろ。 嫌やったら行くのやめるか」
「誰がやめるなんていった!」
不審そうな様子を十三がからかうと、豹馬はすぐムキになって怒鳴り返した。
そんなところが憎めなくて、ついからかいたくなってしまうのだ。
「ところでな。 小介が行きたない言うてごねとるんや。 なんとかしてくれへんか」
そういって豹馬をあおり、興味はないと言い張る小介にバイクの面白さをたっぷり教授させることにしたのだ。
子供らしいところの少ない小介に何か夢中になれることでも、という気遣いでもあった。
バイクに関する知識が小介にどこまであるのか確認する意味もかねて、舗装道路をオンロード、山道や河原などをオフロードというところから始めた。
駐輪場へ連れていき、所員たちが通勤や所内移動用に使用しているバイクを見せながらバイクの種類を説明していく。
「豹馬さんはなぜオフロードバイクに乗っているんですか」
純粋な小介の問いに、豹馬は遠い瞳をした。
「俺が初めて乗ったのはオンロードバイクのタンデム (二人乗り) だったけど、ハンドルを握ったのはモトクロッサーだったから …… かな」
バイクを覚えた当時の豹馬はまだ小学生だったため、私設のオフロードコースで練習していた。 オンロードマシンにも乗りたかったのだが、教えてくれた人達の中に白バイ警官がいて 『免許の取れる十六歳になるまで路上はお預け』 と言われていただけだ。
GPも耐久レースも観戦に行ったことはあるし、ピットやパドックを見学したことだってある。
もっとも、今でもオフロードマシンなのは 『約束を守って』 ではない。 パトカーや白バイを撒くのに路面を選ばず、応用が利くからなのだが …… 。
幼い頃のことを思いだしたせいか、話をする豹馬自身が夢中になっている。
しかし、専門用語を多用しない分かりやすい話だった。当時、小学生だった豹馬が飽きずに興味を持てるようにと配慮された内容で教えられたからだろう。
リビングルームでの二人の話を聞くともなしに聞いていた十三達までが、引き込まれる程だ。
結果、五人揃って出かけることになった。
ガルーダとの決闘以来、久しぶりに見る豹馬の楽しそうな顔だった。
しかし
。
せっかくの休養日もどれい獣の出現で取り消しとなり、さんざんな日になった。
GPレース観戦から四日が過ぎた。
戦線離脱の罰則として、一週間の自由時間剥奪処分として特別メニューによる厚木基地のアクロバット飛行チームとのドックファイト訓練を命じられた。
その訓練に向かう三日目の朝、四ッ谷博士からバイクの改造許可が出た。
いつか言い出すだろうと覚悟していたらしい四ッ谷博士は、豹馬に気づかれないようにいろいろな方面で情報収集を行い、様々な準備を進めていた。
襲撃が続き、許可を出すタイミングを失っていたが、ここに来て不十分だった準備も一通り整ったのだ。
「豹馬、この条件を呑めるか?」
許可する代わりにと五つの条件が提示された。
これまで外出にあたり、コネクション側からの制約は特になかった。
黙認されていた、という方が正しいだろう。
それというのも南原博士急逝後、無許可であっても管制官に告げてから出かけていたし、音信不通になったこともなれば、警報から十分以内に帰還できなかったこともない。 もちろん出撃できるだけの気力、体力、精神力は維持していたから、奴隷獣来襲時に不都合が生じたことはなかった。
左腕が麻痺を起こしたときを除けば、トラブルは皆無である。
バトルチームのリーダーとしての自覚と責任感はあっても、ツーリングをやめることはできない。 やめたら自分が自分でなくなってしまうから …… 。
誰かに公約したわけではないが、両立させるために豹馬が自らに課し守ってきたことだった。
それとは別に、四ッ谷博士は五つの条件をつけたのだ。
1.整備要請は必ず総務部総務課のスタッフを通して行うこと。
2.部品代及び人件費は豹馬が全額、負担すること。
3.改造ポイント決定には五人以上、参加すること。
4.整備完了後の点検は三人以上で行うこと。
5.整備完了の請求を絶対にしないこと。
一晩考えて 「条件を飲む」 と答えた豹馬は、四ッ谷博士から掲示板に募集ポスターを掲示することを知らされた。
上杉が豹馬と話をした二十日後、コネクション内の掲示板に一つの通達が出た。
内容は 『バイク改造参加希望者募集』 。
「説得に成功したんだ。 豹馬さん」
早速、上杉が応募に行くと先輩たちがすでに来ていた。
アンケートの質問事項として豹馬の要望が記されており、改造ポイントを記入するようになっていた。 バイクを専門に勉強した所員などいないだけに少しでも解る人間に担当させようというのが狙いである。
応募者は技術開発部、資材部、医療部、生活部など様々で、三日後に締め切った時には四十八人に上っていた。
登用の選考条件は、武器関係やバトルマシン専属整備士ではないこと、上司の了解をきちんと取り付けていること、そしてアンケート結果の順に各課二名まで。
応募者の中からこの条件を満たす所員を二日間かけて、選ばれたのは十五名。
所属の内訳はマシンの整備員や建物の補修員をはじめ、事務関係者、所内警備員、 〈ジェットミニ〉 のパイロット、清掃員、薬剤師、耳鼻科医、眼科医など実に多彩である。
その中には先日の上杉も含まれていた。
バトルチーム解散から数年の後
。
バイクショップを経営することになる豹馬と上杉との縁は、このときから始まった。
F i n