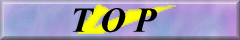豹馬がガルーダ将軍に両腕の神経を焼かれた日から、今日で3日。
南原コネクション内は、今までにない異様な雰囲気に包まれていた。
情報部調査1課から調査5課まであるうちの、1課と2課、そして3課の所員が電算課に詰めるか出かけるかして、必至で調べ物をしている。
それが 『豹馬の今後』 、ひいては明日の地球の命運を担うものと信じているからであろう。
豹馬負傷の一報が入ってから、まもなく70時間が経過しようとしていた。
四ツ谷博士は管制司令室の所長席にすわり、正面スクリーンを眺めながら、隠し持ったウイスキーを舐めていた。
「博士、これからどうなさるおつもりですか?」
「どう …… とは?」
解っていながら聞き返す博士の態度に、不安が募り、つい解りきったことを口にしてしまった。
聞いてきたのは、管制司令室オペレーターの中で副主任を務める男だった。 夜勤担当者への引継ぎを終えた最後の一人が司令室を出て行くのを見届けた直後のことである。
「豹馬さんのことです。 いつまでも脳波操縦装置で戦っていけるわけがありません」
それは誰もが言えずにいた不安の原因。
「しかし …… 戦えなくなったから 『ご苦労様でした、お帰りください』 というのもなぁ」
「情に負けていては、キャンベル星人に勝つことは出来ません」
「一応、人事部に後任候補のリストアップをするように頼んではおるが …… 。 気が進まんというのが、ワシの本音じゃ」
「博士!」
交代したばかりの通信士やレーダー監視員たちを思わず振り返らせるほどの声にも、博士の態度は変わらなかった。
しかし、それまでの酔いの混じった眠そうな雰囲気から、アルコール分の抜けた真剣な気配に取って代わっていた。
「豹馬に限らず、他のメンバーが傷つき倒れる可能性は南原にも解っておったはずじゃ。 なのに敢えて後任候補の名を残していかなんだのは、それなりの理由があってのことじゃないかのぉ」
きっぱりと言い切られてしまえば、確かに言われる通りなのだ。
豹馬負傷の知らせに直ちに後任選出にかかったのだが、バトルチームメンバー候補者に関する全データが消去されていたことが判明した。
当然のことだが、現在の五人に正式に決まるまで 《バトルマリン》 はともかく、残り四機のパイロット候補にあがり、不採用となった者たちが何人かいたはずなのに …… である。
「おそらく、五人に自覚を持たせるためだったのじゃろうが …… 」
『自分達がやらなければ代わりはいないのだ』 という責任感を持たせるために、準メンバーを用意しなかったのであろう。 そのことは、初出撃から帰還した後に行われた雇用契約の際に、書面と口頭で五人に通知されていた。 しかし ……
「まさか、データもないとは …… 意外じゃった」
かといって、急場しのぎに国連軍兵士を採用しようとは思わない。
二代目所長としての役目を引き継ぐ際に目を通した、山のような書類の束の中にはさまざまなものが入っていた。
《コン・バトラー》 の設計図や南原コネクションの見取り図はもちろん、コネクション業務に関する収支決済、従業員の就業規則、経済界における出資協力者、医学や科学分野の研究学会での賛同者、各国の司法行政とのつながり、果ては国際犯罪結社の動向まで、善と悪、表と裏、清濁合わせて取り込んだ、ありとあらゆることが記されていた。
コネクションを組織として立ち上げる以前の南原博士が、幾多の妨害工作すべてを 『未遂事件』 に変えた情報網なら、豹馬を救えるかもしれない。
それは 『もしかしたら …… 』 と期待を抱かせる研究論文であった。
「それにな。 あいつらの姿を見ていたら、とてもじゃないが、やめろとは言えん」
四人のうち、ひとりでも豹馬の交代を願うものがいれば、やむをえないと思っていたが、誰一人博士の元を訪れるものはいなかった。
逆に豹馬のハンデをカバーするべく今後の対策を検討しているという。
どちらかといえば、考えるより先に身体が動くタイプだっただけに、理路整然と考えをまとめて操縦するというのは、至難の業だった。
しかも最高速マシンを誇る 《ジェット》 だけに、角度が一度ズレただけでも、とんでもない誤差が生じてしまう。
それを制御すべく、豹馬は負傷した翌日からシュミレーションルームにこもりきりだという。 昨日は小介と大作が、今日は十三が理学療法士と共に訓練に立ち会っているという。
他のメンバーはちずると共に資料室で、自身のマシンで制御できる部分とそうでない部分を確認し、タイミングの取り方や動きの基本パターンを分析し、合体後の動作にかかる負担だけでも減らそうと懸命だった。
そんな彼らの思いを踏みにじることは出来なかった。
さかのぼること3日前、豹馬が負傷して6時間がすぎた頃。
リビングの一角に陣取り、ぼんやりと物思いにふける夕食後のひと時。
いつもなら、本日の戦闘記録を確認しながら反省会が行われるが、明日に延期と言われていた。
というのも、豹馬が奴隷獣撃破直後にコクピット内で意識を失ったまま、今だ昏睡状態が続いているからである。 血圧や心拍数などは一般正常値を示しているため、過労ではないかと聞かされていたためである。
消灯までのわずかな自由時間だが、何をしようという気になれず、なんとなくリビングに足が向いた。
ちずるの弾くピアノの音色に誘われてみたものの、彼女の音色にもいつもの精彩はなく、いつしか途切れて暗い雰囲気がリビング内を漂い始めた。
「ねぇ、これから …… どうなるの?」
少し離れたところにある床を下る形で作られたソファに座る青少年三人に、ちずるは声をかけた。 窓際に十三が立ち、通路用にクッションのない部分をはさんで、十三側に大作、反対側に小介が、ぽつんぽつんと座っている。 それぞれの間は2〜4人は座れそうなほど離れていた。
「豹馬しゃん?」
「えぇ」
視線を向けた大作にうなずく。 その表情には不安の色が浮かんでいた。
「普通に考えるのでしたら、交代でしょうね」
「仕方 …… なかよ。 俺達は戦うためば、集められっとじゃから」
小介の言葉を、大作が引き取った。
「ばってん、豹馬しゃんは戦えんいうことはなかとよ」
「それでも、いつまで保つか …… 。 明日、明後日に終戦を迎えるというものではありませんからね」
ピアノの傍からソファへ移動したちずるは、そっと小介側の通路脇に腰を下ろす。
「なんか …… イヤね」
十三は、三人の交わす会話にも加わらず、窓の外に視線を向けたままだった。
十三の中には、自分のミスとの思いがある。
たとえ連れ去られたとしても、豹馬が自らの意志で地球を裏切るとは思わない。
それでも、豹馬の口から《コン・バトラーV》の情報を引き出そうとするのは目に見えているし、何らかの方法で洗脳し地球攻撃の尖兵として取り込まれる可能性もゼロではない。
チームリーダーとしての彼を失う以上の大きな損失につながる。
それを恐れた十三の独断が、今の現状を引き起こしたのだ。
だが、誰も十三を責めようとはしなかった。
それだけに豹馬を戦列から外されないようにするには、どうしたらのいいか …… 。
誰も口にはしないが、思いは同じだった。
もし、今回のことで豹馬が外されるようなことがあれば …… 。
自分達も重症を負い、戦士として不要になればお払い箱になる可能性が出てくる。
他人事ですまされることではなかった。
聞いた限りでは、豹馬の傷の具合は思わしくないらしい。
現在も両腕の治療は続けられているが、切断は時間の問題との見方が強まっている。
何らかの新しい治療技術の実用化でもない限り、既存の医学技術ではどうにもならないというのが現段階での見解であった。
四ツ谷博士の決断次第であるだけに、つらいものがあった。
「ワイらが豹馬にしてやれることは …… なぁにんも …… 」
静かな沈黙が流れる。
「やりきれんなぁ」
十三のその一言にハッとした小介が全員を見回しながら提案した。
「これから資料室へ行きませんか?」
「行ってどぎゃんすっと?」
切り返してきた大作に、楽しそうに説明する。
「手伝うんですよ。豹馬さんを …… 。 《コン・バトラー》 は豹馬さん一人で操縦するわけではありませんからね。 《1号機》 でなければ操作できないことと、他の四機でも操作できることを整理して、豹馬さんの負担を減らすんです」
「たとえば?」
ちずるの問いに、少し考えて答える。
「十三さん、 《コンバトラー》 の腕から行う武器類は 《2号機》 から操作できますか?」
「せやなぁ …… ヨーヨーは無理やけど、ロックファイターやアトミックバーナーとかやったらできるで。 指動かせいうんはアカンけど、両の腕振り回すくらいやったらでけるでぇ。 んーー …… 腹とか目とか、 『ここ狙え』 て言うてくれたら、後は照準とタイミングをはかって引き金引くは可能や」
「つまり、そういうことですよ」
三人の目が丸くなり、いたずらっぽい小介の言葉が続く。
「使う武器や狙うポイントは豹馬さんが決めるとして、発射のタイミングは十三さんが行うんです。 発射した後の 《コン・バトラー》 の姿勢制御も出来る限り、僕達で …… 」
「確かに …… 。 いけるかもしれへんなぁ」
何度か、発射のタイミングを委ねられたことのある十三は、呑み込みも早かった。
ワンテンポ遅れて、ちずると大作も理解する。
「そう …… ね。 いちいち口頭で指示されなくても、ランプか何かで 『次はこの武器を使う』 とかが解れば、フォローは出来るわね」
「多分、一番負担が増えるのは十三さん …… あなたですよ」
いいんですか、と問いかける小介の不安を、十三はあっさり吹き飛ばした。
「んなもん、かまうかいな。そうと決まれば、こないなトコでグズグズしとれんで」
「どの程度のことば、できるんか、データば調べまっしょう」
「消灯前にある程度の情報がほしいわね」
一斉に立ち上がった様子に、小介もうなずき、リビングを後にした。
十三の表情に安堵の色が混じっていた。
《コン・バトラー》の武器の中に、 『手で握って振り回す』 といった類の武器がなかったことが幸いしていた。
合体前の編隊飛行から始まり、腕から発射する銃火器を発射するために腕担当の十三と脚部担当のちずるとの連携、といったさまざまなパターンを想定した訓練を重ねるために …… 。
豹馬負傷から三日目の午前中、4人は図書資料室にいた。
多くない奴隷獣との戦闘記録を広げ、豹馬の攻撃パターンを分析する。
「こうしてみると …… 行き当たりばったりというか、直感というか …… 行動に統一性がありませんねぇ」
「あたりまえや。 アイツは、頭で考えるより先に身体が動くタイプやで」
しみじみという小介を、十三は笑い飛ばす。
「確かに …… 言えてるけど」
4人のため息がハーモニーを作る。 誰の口からも楽観的な意見は出なかった。
操縦システムの改造は、コンピュータ制御の問題でチョコチョコっといじって済むものではなかったからである。
場合によっては、全システムに手を加えなければならなくなるし、万が一、制御システムにバグでも発生すれば 《コン・バトラー》 は彼らの制御の手を離れて悪魔と化してしまう恐れがあるという。
一応、豹馬からの依頼もあわせて、脳波操縦装置による制御負担を減らす方向で、検討を始めてはいるが、短くても数ヶ月、長ければ数年単位の時間を要するとの判断が下されていた。
いつ攻めてくるか判らない奴隷獣に対抗する手段としては、採用できない選択である。
現在の豹馬は、流動食で栄養補給をし、点滴による薬剤投与を受けながら、シュミレーションルームにこもっている。
もともと食事制限はないのだが、幼児のように 『開いた口の中に食べ物を運んでもらう』 という行為を、豹馬が極度に嫌がったためだった。
食欲はあるし、若く元気がいい上に、普段からバイクで転び慣れているせいか、身体の回復力はかなりなものだという。
怪我の翌日、目を覚ました豹馬は、傍にいた医師に 「 《ジェット》 を降りる気はないから」 と宣言、理学療法士を立ち合わせて脳波操縦装置による操縦訓練プログラムの作成を依頼したほどらしい。
だが、気力だけで乗り越えられるものではないことも、判っているのだろう。
ふとした折にもらした 「バイクはもう無理かなぁ」 の一言が胸に突き刺さった。
そこへ …… 。
「バトルチームの皆さん。 バトルチームの皆さん、直ちに医療部までお越しください。 繰り返します …… 」
「どないしたんやろ?」
十三を先頭にいっせいに駆け出した4人は医務室へと向かった。
急いで向かうと、医師や看護婦が右往左往している。 一人の医師が彼らに気づいた。
「おそろいでしたか。 よかった …… 」
「一体、どないしたんや?」
「先程、豹馬さんが …… 倒れたんです」
「なんやて!」
豹馬の病室の前には四ツ谷博士が立っていた。
「どぎゃん具合ば …… なっとるとですか?」
「博士!」
「おっちゃん!」
「うるさい、騒ぐな。 診察中じゃ」
だが、苦しげな様子は変わらない。 何らかの理由を知っている顔だった。
「隠し事はやめてくださいね。 私達の命もかかっているんですから」
ちずるの落ち着いた厳しい声が、四ツ谷博士の視線を呼び戻した。
「判った。 ついて来い。 廊下で話せることじゃないからな」
医師たちが休憩室兼相談室として使用している 【カンファランスルーム】 と書かれた部屋へ入っていった。
「昨日の段階でもらった報告 …… カルテだ」
英語で、しかも専門用語で書かれているため、十三と大作にはチンプンカンプンのカルテだったが、さすがに小介とちずるは反応した。
「かなり …… 危ないってことですか?」
「そうじゃ。 撃たれた場所が場所じゃからな。 命には別状ないものの、肘から下 …… 正確には傷口から指先までの部分が壊疽を起こし始めたようじゃ」
壊疽を起こし始めた …… つまり、腐り始めたということである。
「弾丸ではなく、レーザーで断続的に焼かれた傷じゃからな。 重症の火傷という見方をしておったようじゃが …… 患部が広すぎて表面的なことにばかり気を取られておってな。 傷の深さを見落としておってな …… 」
目を閉じ、一呼吸おいて出た話は聞くに堪えないものだった。
「南原の葬儀のとき、火葬にした後に拾った骨は、箸で砕けるほどスカスカになっとったろう?」
「は … ぃ … 」
「豹馬の上腕の骨はそうなる前、ちょうど肉体が焼けて骨が見え始め、さらに骨の中の成分が焼け始める直前の状態に似ているということじゃった」
最終的な診断結果によると、ガルーダの狙ったヒットポイントは、ライフルの弾丸であれば骨を掠めて貫通しているのではないかとの視方をしていた。
だが、実際に使用されたのはレーザー銃、それも照射量が中途半端に絞られていたため、かなりの広範囲に及ぶものだった。 つまり、皮膚から骨までの全組織が焼かれていたのだ。
現場にいて傷口を最初に目にした十三たちの印象は、確かに表面を掠めたという程度でないことはすぐに解った。 だが、銃創なら何度も見たことのある十三も、医学の心得のあるちずるも、レーザー銃の傷を見るのは初めてだった。
確かに患部は崩れ、膿み崩れたような状態に見えていた気がする。
コネクションから駆けつけた救急隊員たちも、その悲惨さに目をそむけ、患部を覆って一刻も早くコネクションに収容することしか頭になかった。
とてもじゃないが、 『止血の必要がない』 という点に気を配る余裕などない状態だった。
コネクション医療部と電算課が共同で総力を挙げて検索してみたが、レーザー銃を凶器とする症例は数十例しか見つからなかった。
その数少ない症例から解った共通項は 『出血がないときこそ危険である』 。
特に骨に達している場合は、骨を構成する組織が焼かれている可能性がある。
豹馬に当てはまり、すでに手遅れの域に達していた。
たとえは悪いが、治療法としては骨にがん細胞が見つかった場合と同じ処置法をとることになる。
つまり、切断 …… しかない。
「そんな …… 」
蒼褪め、口元をこぶしで隠したちずるは、泣きそうな顔をしていた
「なんとか …… ならないんですか?」
「出来るもんなら、とっくにやっとるわい!」
悔しげな博士の声を受けて、小介がポツリとつぶやくように言った。
「たとえ、非合法な方法であっても …… 豹馬さんを助けることは …… できないんですか?」
四ツ谷博士の瞳に一瞬鋭い光が走り、小介に仲間の視線が集まる。
自分が何を言ったか、気がついたのだろう。 心の内の葛藤に決着をつけるためか、一呼吸置いた小介は、思い出しながら言葉にしていった。
「アメリカの大学にいたとき、雑誌か何かで見たことがあるんです。 詳しいことは覚えていませんが、クローニングに代わる技術の研究者がいる……って。 確か、 『ロボットとサイボーグは限りなく近づいていくだろう。 だが、両者には決定的な違いがある』 …… とか何とか …… 」
「どういう意味なの? それ …… 」
ちずるの問いに小介は、視線をむけた。
「ボクの専門分野ではありませんから、詳しいことは …… 。 ただ、工学分野の学会では相手にされず、医学会では逆に人間の倫理に触れるとかで、どちらからも追放処分になったらしくて …… 。 論文発表の雑誌の中に 『学会追放』 という文字が大きく派手に載っていたのが印象に残っているだけです」
「いつ頃の話じゃ?」
四ツ谷博士の問いに、小介はしばらく考えた後、言った。
「はっきりとは …… 。 ただ、ボクがアメリカに留学した後、コネクションからのスカウトを受ける前でしたから …… 2〜3年くらい前の話だと思います」
目を閉じた四ツ谷博士は、硬い表情で考え込んでいた。
「博士! こちらでしたか」
調査2課の所員が駆け込んできた。
「博士のおっしゃっていらした研究機関に所属していたという方が見つかりました」
「本当か?」
音を立てて立ち上がった博士の前に立ち、メモを見ながら報告する。
「はい、勝田博士のもとで助手を務めていた方たちでしたが、研究室閉鎖後は何人かの同僚と共に、形成外科の分野に対象を絞ることによって細々と研究を続けていたそうです」
「招聘できるか?」
「今、調査二課の課長が直接交渉に向かっています」
「解った。 豹馬の現状のカルテを届けて、何が何でも説得してくるんじゃ」
「了解!」
敬礼して再度、飛び出していく所員を見送った4人は呆然としていた。
「な …… なんだったんですか?」
息をつき、椅子に座り込んだ博士の表情には、先ほどのような悲壮感は見られなかった。
むしろ、希望を見つけたように安堵の雰囲気がある。
「どないなっとるんや?」
「おそらく …… 今の小介の話と同じじゃろう。 たとえ非合法な技術でも、救える道があるのなら …… とな。 探させておったんじゃ。 今のが、その報告じゃよ」
「じゃあ …… 」
「あぁ、後は …… 間に合うかどうか …… それだけじゃ」
縫合手術は、切断直後でなければ処置の出来ない場合がある。 それを見越して今まで我慢させていたのだ。
「でも、豹馬さんはこのこと …… 」
「一応、話してはある。 人体実験となる可能性の高い、非合法な方法になるかもしれんし、研究中のために副作用で苦しむことになるかもしれんということも含めてな。 しばらく考えておったようじゃが、豹馬の奴、こう言いおったわ」
ニヤリと悪戯っぽい笑みを浮かべた。
『バイクに乗れるようになるんなら、かまわねぇ』
その言葉に4人は唖然としてしまった。
「確かに …… 豹馬らしいわな」
十三の言葉に顔を見合わせ、思わず笑みがこぼれた。
考えてみれば、確かにそうなのだ。
座席に座ってコクピットをにらんでいるしか出来ない、今の身体ではバイクなど乗れるわけがない。
バイクに乗るには、ハンドルを握る腕がなければ不可能だし、微妙な体重移動を行うためには身体のバランス感覚も必要になってくる。
茶化した言い方をしているが、豹馬にとって 『バイクに乗りたい』 という思いこそが、これから始まるつらい機能回復訓練を行う上での精神的な支えであり、最終目標であり、励みになっていくのだろう。
豹馬の強い意志と固い決意を表していた。
数時間後、人工細胞研究者の快諾を取り付け、来日予定を伝えてきた。
手術は三日後に決定。
豹馬に移植する新しい腕を作るのに約60時間を要し、輸血に必要な血液の確保、脊髄への影響、薬物や拒絶反応による内臓機能への負担も考えられるため、さまざまな検査が行われた。
特殊な有機物質で骨格を再生、そこへ豹馬自身の身体から採取した細胞を培養増殖させていくのだ。
特に神経を尖らせたのは、人体への本格的な移植手術は前例がないという点だった。
動物実験は成功しているものの、ここ1〜2年の間に行われた人体への移植手術例はゼロ。 当然ながら、身体的な成長が見込まれる年齢の移植例は皆無だった。
完全に人体実験の被検体である。
今回は整形外科の分野である、骨と筋肉に関する手術だが、いずれは臓器移植にも生かせるようにしたいらしく、将来性の期待される技術でもある。
それだけに、手術中にどんなことが起きても対処できるよう、直接関係ないと思われる分野の医師たち ――― 脳外科、心臓外科、循環器科、腹部外科、内科、整形外科など思いつく限りの専門医が集められた。
一方、豹馬も応急処置が施され、意識を取り戻すまでに回復。 手術に耐えうる体力があるかどうかの確認と手術の許諾書に署名捺印を行ったあと、手術前の事前処置を施された。
そして手術当日。
奴隷獣をコネクションに近づけてなるものかと、コネクション全体が異様な緊張感に包まれる中、警戒態勢が敷かれ、四ツ谷博士は手術に立会い、十三は司令室で、大作は航空観測室で、ちずるは海底観測室で、小介はコンピュータ技師と会議室で落ち着かない時を過ごしていた。
手術開始から20時間が経過し、豹馬の手術成功を伝える館内放送が流れた。
一同から安堵の声が漏れ、手術室前へ駆けつけた4人は豹馬が無菌室へ運ばれたと聞き、窓越しに会わせてもらった。 麻酔から覚めない豹馬の寝顔は、普段の子供っぽい言動からは想像できない、年相応の穏やかな落ち着いた表情をしていた。
細かな注意点はあるものの、特筆すべき点もなく、術後経過も順調。
豹馬の腕から採取した細胞が切断面と融合、血液の流れも他の部分への悪影響もなく、順調な回復を見せた。
無菌室3日、集中治療室2日を経て、いくつかの免疫検査の後に一般病棟へ移され、同時に無菌室や集中治療室では動かさなかった筋肉のリハビリも開始し、それらの筋肉を使うことによって生じる血液の流れがどのように影響するかといった検査も並行して行われた。
その間、バトルチーム4人だけで出動しなければならないような事態もなく、不気味な、しかし穏やかな日々が続いていた。
豹馬が一般病棟で過ごすようになって10日め。
ギプスと包帯がはずされ、初めて動かしていいという許可がでた。
恐る恐る動かしてみた指は …… 。
「動く。 動きます。 博士 …… 」
事件以来、豹馬から消えていた笑顔が戻った瞬間だった。
そこへ …… 。
「人工細胞開発者の勝田博士と名乗る方がお見えです」
それは豹馬にとって、新たな試練の始まりだった。