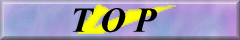甲高い金属音が、あっという間に右から左へと駆け抜けていった。
間違いなく100キロ以上のスピードが出ている。
もちろん、ここはサーキットではない。
海岸線のすぐ横を、まっすぐに伸びている舗装道だ。 しっかり対向車線の存在する一般道である。
街路灯一本ない真っ暗な道路を、二つのライトが排気音まで置いていきそうな勢いで疾駆する。 光の尾を引いて突き進む様は、まるで宇宙空間を往く彗星のようだ。
やがて凄まじい勢いで、カーブが迫ってきた。
一気にいくつかギアを落としたらしく、エンジンの回転数が跳ね上がる音が響いてくる。
と、僅かなタイムラグの後もう一回、似た音が辺りに反響した。
どうやら猛スピードで海岸線を飛ばしていたのは、一台の車ではなく二台のバイクであったようだ。 そう錯覚させるほど、二台は僅かなぶれもなく並走していたのである。
減速を遅らせた分、一台がもう一台よりも先にコーナーへと進入していく。
ここから先は、一転してワインディング・ロードだ。
様々なアールのコーナーが次々と現れる。
減速と加速、ギアの上げ下げをめまぐるしく繰り返さなければならない。 さらに車体を右へ左へと振る。
スピードを維持しながら。
対向車の影を気にしつつ。
パッシングポイントは、そう幾つもない。
先を行くライダーが、第一コーナーに進入する時にギリギリまで減速を我慢した理由がそこにある。
「さすがね、豹馬」
負けず嫌いがライダースーツを着ているようだと形容される彼女、荒川由美の口からは案外素直に賞賛の言葉が出てきていた。
もっとも、先行する豹馬の耳に届く間もなく風に乗って、遥か後方に吹き飛んでいってしまったが。
「 … でも … 」
面目躍如的な一言を付け加えると由美は、その口元に薄く笑みを浮かべる。 が、その眼は鋭さを増しただけで、決して笑ってはいなかった。
道はさらに様々なコーナーを繰り出して、彼等に挑戦してくる。
しかもさっきからずっと、登り勾配が続いていた。
こうなると追いかける側は、より冷静に機会を窺わなければならない。
あせりは禁物だ。
サーキットならば、道幅の全てを使ったコーナーリングが可能だし先行車に揺さぶりをかけることもできるのだが、一般道においては対向車が来る可能性がある以上、コーナーへの進入はアウト・イン・アウトが基本となる。
日本の道路は左側通行なので、対向車側からインに切り込んでいき出口で多少アウトに膨らんでも、センターラインをなるべく超えないように脱出していくのが、一番リスクが少ないからだ。
しかしそれが、夜という条件下であればどうなのだろうか。
由美は目の前を疾走する豹馬のバイク、そのテールランプを睨みつけながら追走していたが、特にコーナーリング時の挙動に彼女のそれと微妙なずれがあることにふと気が付いた。 由美より先行しているのに、コーナーに対応したアクションが同じタイミングかややもすると僅かに遅れているのだ。
次々と目の前に出現するコーナーをクリアしつつ、エンジン同様頭もフル回転させる。
豹馬の速さは、確かに天才的といってよい。
が、コーナーの先を読みながらギアを選択し、ブレーキとアクセルをコントロールしながらタイヤのグリップを維持してクリアしていく由美の走りと比べて多分に感覚的なのではなかろうか。
ハイスピードに対する圧倒的なまでの耐性と、その中でも的確に周囲の状況を把握できる動体視力。 そして路面の状態やマシンの挙動に、迅速に反応して対処する反射神経。
同等なセンスを持ちながら、それを理解した上でバイクを駆る由美と、どちらかというと無意識に行使している感のある豹馬。
持っている資質を総動員してバイクをねじ伏せるようにしながら、より先へ、より速く。
それが豹馬の速さの全てではないか?
そしてそれが、ほんの僅かなタイムラグをもって機能しているのだとしたら。
普段なら考えもしない手段だが、夜が味方してくれるかもしれない。
由美は、決断した。
葵豹馬にとって、バイクは全てではない。 スピードが出せるのなら車でも構わない。
便宜上、暴走族に入っているが、といって暴走することで世間に対するストレスを発散するタイプとも違う。
だから仲間とつるんで走ることはあまりなかった。
彼の中にあるのは、とにかく前に進むこと。
より先へ、より速く。 もっと先へ、もっと速く。
そちらに何があるかは問題ではない。
一分一秒でも速く、前に進むことが重要なのだ。
小さい頃、棄てられた自転車を拾ったことがある。 補助輪の付け根が駄目になっていてチェーンも緩んでいたが、何とかまだ走る代物だった。 ペダルを漕いでは転び、引き起こしてはペダルを漕ぐ。 そうこうするうちに、自転車に乗れるようになっていた。
嬉しくなった彼は、疲れて足が動かせなくなるまでペダルを漕ぎつづける。
自転車に乗れるようになった自分は、どこかで必要とされているのではないか。
誰かの役に立つのではないか。 そんな漠然とした期待を、胸に抱いて。
でも、見つかったのは一人っきりの豹馬。
誰も彼を必要としてくれなかった。 誰かに必要だと言って欲しかった。
彼をスピードへと駆り立てるもの、それは天涯孤独な彼の寂寥感と早く自己を確立したいと願う焦燥感に他ならない。
二台のバイクは、左車線を最大限に利用してコーナーリングしていく。
特に最もアウトに膨らむ瞬間に対向車とすれ違う時など、誇張抜きに擦れるほどに接近する。 その一瞬、運転手の驚愕の表情を動体視力の優れている彼等は、きっちり捉えていた。 自分たちの暴走をどこか醒めた目で見ている部分を持ち合わせている由美は、思わず苦笑。 しかし豹馬は、目で一瞬追いかけただけ。 走ることだけに気がいっているようだ。
対向車のライトが最初はぼぅっと、やがてスポットライトのようにパアッとこちらを照らし出す。 すれ違う対向車。 この一連の流れの中で、由美はあるタイミングを計っていた。
孤児院で育った豹馬と同様、由美にも両親がいない。
が、彼女には一人の兄がいる。 この世にたった一人だが肉親がいるだけ、豹馬よりは恵まれていたと言えるかもしれない。
彼女の兄は、荒川徹。
あるバイクメーカーのワークス・ドライバーをしている。 来年には国際デビューも決定している、若手のホープだ。
レーサーを兄に持つ彼女が、人生の指針として兄の生き方に倣おうとするのは当然の帰結と言える。 由美は兄のようなレーサーとなることを夢見ていたし、その気持ちに理解を示してくれた兄の指導を受けていた。
速さでは、天才的な豹馬に敵わないかもしれない。 単に抜いたところで、意地でも抜き返してくるだろう。 だが良く言えば真っ直ぐ、悪く言えば単純な豹馬だからこそ、レースの駆け引きに長けている彼女は一発に賭けてみることにしたのだ。
何事にも終わりは来る。
永遠に続くかと思われたワインディングもあとコーナー一つで終点、その先には展望台と駐車場があり、そこの入り口がゴールラインだ。
このコーナーはヘアピンほどではないが、アールのきついカーブなのでかなり減速して進入しないとマシンのコントロールを失う可能性がある。
由美が仕掛けてくるとすれば、コーナーを曲がり切ったあとの立ち上がりだろうと豹馬は思っていた。 だからコーナーリングの最中に由美が並んできた時、彼が自分の目にしたものをすぐには理解できなかったのも無理はない。
「なにぃっ!?」
思わず驚きの声まで上げていた豹馬だが、すぐに気持ちを切り替えたのはさすがと言うべきだろう。 コーナリング中の動揺は命に関わる。 彼のバイクの前輪は、ピクリとも動かなかった。
由美は、最終コーナーに対向車線を無視してガードレールぎりぎりまから進入、対向車がいてもライトの明かりが見えてからすれ違うまでの明るさの変化から、判断して避けられるようにタイミングを計った上で、道幅の全てを利用したコーナーリングを敢行したのである。
ブレ−キングのタイミングはもちろん、道路の一番右端から進入することでスピードを豹馬ほど落とさずに済み、その結果コーナーリング中に彼と並ぶことに成功したのだ。
「やけに、おとなしくついて来ると思ったぜ」
そうひとりごちながらも、豹馬は由美の勝負度胸に舌を巻いていた。
口元には知らず知らず、苦笑が浮かんでいる。
「この豹馬さまをアウトからかわそうってのかよっ!」
そう叫んだのは、自分に活を入れるためでもあったのかもしれない。
「いけるっ」
由美にとって、手応えは充分だった。
海岸から展望台までのこのコースを、豹馬と走ったのはもちろん初めてではない。
どちらかというとはみ出しものの集まりのような暴走族からもはみ出していた二人は、妙にウマが合いつるんで走ることが多かった。
そんな彼らが表立って非難されないのは、ひとえに走りや荒事で抜きん出ているからに過ぎない。
もちろん出番とあれば、彼らも拒むことはなかった。 多少渋ることはあったにせよ。
そんなわけで普段は、集団に混じることなく好き勝手にしていることが多かったので、ここでちょっとしたレースをやらかしたことも何回かある。
初めての時は、由美が勝った。 ちょうど今日の豹馬のように第一コーナーへ先に入って、ずっと抜かせずにゴールしたのだ。 この時の豹馬の悔しがりようは見物であったが、その後由美は勝っていない。 そこが豹馬の恐ろしいところだ。
が、だからといってそれ以降、由美がここまで勝負に拘ったことはなかった。
ただ一緒に走るのが、楽しかったのかもしれない。
兄に教わるようになってからは特に、無敵だった彼女に泥をつけた唯一の存在、葵豹馬。
実際には彼に強烈に惹かれていたことを、この時の由美は絶対に認めなかったろうが。
何故この時に限って、豹馬に勝ちたいと思ったのか。 由美本人にも自覚はなかった。
この最終コーナーを曲がりきれば、300メートルの直線と最終コーナーと逆にカーブしている駐車場の入り口のみ。
勝てる、と思った由美の視界がやにわに明かるさを帯びてきた。
「えっ … 」
迂闊と言えば、迂闊であったかもしれない。
間延びしたS字カーブのようになっているため、対向車がカーブに差し掛かってライトの軸線が直線道路を照らし出すまで、由美の目に全く入らなかったのだ。
このパターンは、考えてなかった。
対向車はともかく、由美のバイクは尋常ではない速度でコーナーを立ち上がっている。
お互いの距離は、あっという間に縮まった。
「くっ!」
咄嗟に左側へと体重をかける。
間一髪!
何とか対向車を避けて、豹馬の前へ。
が、バイクが由美のコントロール下にあったのはそこまでだった。 無理に体勢を戻したのがきっかけになり、後輪が滑り始める。 それを抑えようと当てたカウンター・ステアが後輪に掛かったパワーを相殺しきれずに、ハイサイドを引き起こして暴れ馬のように由美を振り落としてしまったのだ。
もはや彼女に出来ることは、剥き出しの頭を守るために身体を丸めることしかなかった。
「危ねえっ!」
そう叫んだ声が、由美に届いたとは豹馬も思ってはいない。 ましてや自分が、何か出来ると考えたわけではないのだが。
ワンテンポ遅れてコーナーから立ち上がった彼は、危機一髪で対向車をかわした由美を見ても安心しなかった。
案の定、彼女は暴れるバイクに振り回された挙句、空中に舞う。
しかしバイクから手を離してしまったタイミングが、良かったと言えるかどうかは判らないが、上に放り出されたのが幸いしたようだ。
豹馬はなんとか由美の下に潜り込むことに成功、空中で彼女をキャッチしたのである。
かなりのスピードで突っ込み、人を一人抱え込んでバランスを崩さなかったのだから、超人的なバランス感覚の持ち主であると言えよう。
豹馬の腕の中で、由美は怯えた小動物のように身を固くして僅かに震えていた。
背後で地面を転がりながら、バラバラになる自分の愛車も目に入らない様子で。
「バッキャロー! 死にてえのか?!」
展望台のそこここにある、木で出来たベンチの一つに座らされて呆然としている由美に向かって、いきなり豹馬は吼えた。
「あの状況で、俺がお前を助けられるとは限らなかったんだ。 一歩間違えれば、お前自身もああなるところだったんだぞっ!」
彼が指差した先に、スクラップと化したバイクの残骸が見える。 さっきまで自分と一体になって、疾走していたとはとても思えない。
「 … ごめん」
うなだれて、ぼそっと一言謝った彼女を見下ろして、豹馬は溜め息をついた。
「いったいどうしたんだ? 由美らしくもねえ」
我知らず、由美の口元が綻んだ。
「あたいらしくない?」
顔を上げた彼女の目から、涙が頬を伝う。
「あたいにだって分からない。 何で今日に限って豹馬に勝ちたくなったのか」
「 … おい、由美」
「ううん、らしくないっていうなら、レーサーを目指すあたいが豹馬に勝ちたいって思わなかったことの方が、よっぽどらしくないんだ」
「 ……… 」
「ここでの競争だって、最初に勝ったきり豹馬には勝てなかった。 仮にも勝ち負けが絡んでいるのに豹馬の背中ばかり眺めていたくない、そう感じていたのかもしれない」
涙を流しながら心情を吐露する由美に、かける言葉を豹馬は持ち得なかった。
「いつか兄貴と同じ舞台に立ちたい。 それがあたいの夢なんだよ」
自分が泣いていることにようやく気付いたかのように、両手で顔中を擦り始める由美。
「豹馬を越えたい。 そして兄貴に近づくんだ」
呪文のようにつぶやく由美。 豹馬に対する劣等感は、そのまま壁となって夢を実現するのを妨げる障害となっていたようだ。 それでも多少は涙が洗い流したのか、暫くして顔を上げた時の由美は、すっきりした表情をしていた。
「ねえ、豹馬?」
「ん?」
「なんであたいは、泣いてるんだろうね … 」
心底、自分の涙が不思議であるらしい。
「バッキャロー、知るかいっ」
困惑した豹馬の一言に、由美はフッと微笑んだ。
「お礼が遅れちゃったね、助けてくれてありがとう」
「おう」
豹馬の買ってきた缶コーヒーを口にすると、由美は突然聞いてきた。
「ねえ、豹馬」
「なんだよ」
「豹馬の夢は何?」
いきなり自分の事を聞かれて、豹馬は答えに窮した。
「 … 分からねぇ」
偽らざる本音である。
「レーサーになろうと思ったこと、ない?」
「ねえなぁ」
自転車から始まって、バイク、車と乗ってはいるが、レーサーになろうと思ったことはない。 豹馬のあっさりとした回答に、由美は苦笑する。
ちょっと寂しそうに、多少安心も滲ませながら。
「由美には悪いけど、同じところをグルグル周るのは性に合わねぇ」
「そっか …… そうだね」
自分でも、何聞いてるんだろうと思っていた。
この先このままでは、枝分かれしてしまう二人の進路。 その確認なのか、それともバイク以外の共通点を探そうとしていたのか。
「これだっ、てものがねえんだ。 俺が完全燃焼できるもの、命を賭けられるものって何なんだろうな」
由美に向かって発せられたものとも、独白とも取れる何気ない口調で豹馬が言った。
それが見つかるのは、この一週間後。 そしてそれに呼応するように由美のスポンサーが見つかり、二人はそれぞれの夢に向かうために儀式を受けることになる。
滅多に自分のことを話そうとしない豹馬が、ぼそっと自分の心情を口にしている。
由美には、いくつか聞いてみたいことがあった。 今なら答えてくれるだろうか。
けれど、由美が何か言うよりも早く豹馬は立ち上がると、
「そろそろ帰ろうぜ。 朝になっちまう」
そう言われると、由美は断れない。 彼女のバイクがオシャカになってしまった今、豹馬に乗せて行ってもらわないと帰れないのだ。
こうして、由美は豹馬の心の奥に触れる機会を永遠に失ってしまった。
「由美っ、しっかりつかまってろよ!」
バイクの排気音でかき消されないように、豹馬が大声で言う。
「うん」
彼女の返事は小声であったが、彼の背にピッタリ寄り添っているからであろうか、ちゃんと伝わったようである。
来るときと違って、さすがの豹馬もあまり無茶なスピードは出さなかった。 といってもあくまで、この二人の基準においてであったが。
「夢っていえばさぁ」
思い出したかのように、豹馬が言った。
「ん?」
由美は物憂げ。
「これは夢 … だったかもなぁ」
「これ?」
「タンデム」
「ああ … ふふふ」
何のことを言っているのか分かると、忍び笑う由美。
「なんだよ」
豹馬としては、心外であるらしい。
「豹馬らしくなぁい」
「ちぇっ、そうかよっ」
「それに、あたいの柄でもないし」
そういう割に、さらに強くしがみつく由美。
「乗せてもらうだけじゃ、満足しねえもんな。 由美女王様は!」
「あたりまえよっ、彼にするならあたいについて来れるほど速い男じゃなきゃ」
「へぇ。 で、どっちが先を走るんだ?」
「あたいっ!!」
海岸線に出てさらに加速したバイクは、より甲高いエキゾースト・ノートを響かせて疾走する。 こうなると今までのように会話までは出来ない。 だが、二人の笑い声だけは排気音と一緒に尾を引いて遠ざかっていった。
余談ではあるが、自分を賭けられるものが夢であるならば、バトルジェットのパイロットにしてコンバトラーVの操縦者となった葵豹馬は、夢を見つけたと言えるだろう。
荒川由美をはじめ、払った犠牲も多かったが。
それともう一つ、密かな夢のほうだが。
バイクのスロットルを空ぶかしさせて、エンジンの吹け上がりをチェック。
満足すると豹馬は、タンク部をポンと叩いた。 そこへ、甲高い金属音を響かせて一台のヨーロピアンバイクが、緑色の線を引きながら走ってくる。
「お待たせっ! 豹馬」
カラフルなライダースーツに身を包んだ南原ちずるが、ヘルメットを片手にニッコリ。
「おう」
何故かちょっと諦め顔の豹馬が、返事を一言で済ます。
『俺の好きになる女の子はみんな、タンデムしてくれるタイプじゃないらしいぜ、由美』
そうひとりごちると、
「行くかぁ!」
「うん!」
頷いてヘルメットを被るちずるを確認すると、豹馬は初夏のちょっと強い日差しの中でバイクのスロットルを思いっきり開けた。