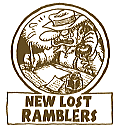 |
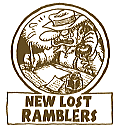 |
| ■ NEW LOST RAMBLERS |
| ■ 2009年3月13日(金) |
Karen Dalton 『It’s So Hard To Tell Who’s Going To Love You The Best』 |
| 曲目 | |
 |
01. Little Bit Of Rain 02. Sweet Substitute 03. Ribbon Bow 04. I Love You More Than Words Can Say 05. In The Evening 06. Blues On The Ceiling 07. :It Hurts Me Too 08. How Did The Feeling Feel To You 09. Right, Wrong Or Ready 10. Down On The Street |
| ♪1970年代、わが国のロック・ファンの間からシンガー・ソングライター・ブームが沸き起こり、ファンたちはジェイムズ・テイラー、ジャクソン・ブラウンといったメイジャーな歌手などの活躍から、やがてフォークをルーツとするローカルなシンガー・ソングライターのレコードを漁り始めた。スポットを浴びることなく活躍している素晴らしいミュージシャンのレコード発掘作業だった。こうした背景からひとりの女性歌手の存在がにわかにクローズアップされた。 |
| その名は、カレン・ダルトン。アルバム名は『In My Own Time』。1971年、パラマウント・レコードから発売されたこのアルバムは、ボブ・ディランやザ・バンドの活躍でお馴染みのウッドストック録音ということもあって、熱心なロック・ファンに注目を浴びた。カレンのスモーキー・ヴォーカルは、ロックやフォーク、ジャズといったジャンルを越えた独自の味わいでうたわれ、バックをサポートしたエイモス・ギャレット、ジョン・サイモン、ビル・キースなどの好演もあって、アルバムはいつしか「名盤」と語られるようになった。そうした最中、熱心なファンは、カレンのアルバムがもう一枚存在することを突き止めた。つまりデビュー盤が発売されていた、というわけだ。この情報は、カレン・ファンにとっては青天の霹靂だった。話題となったデビュー盤は、惜しくも廃盤の憂き目にあっていて、入手困難盤と化していた。幸いカット盤でアメリカから購入したファンは、セカンド・アルバムと同様、個性あふれるカレンの気だるいブルースに涙したという。その後、口コミでデビュー盤の素晴らしさに気がついたファンは、もう「幻」と化していたアルバムを懸命に探すはめになる。 |
| リアル・タイムでの思い出話はさておいて、カレンの生い立ちから話を始めていこう。80年代になると、カレンの消息は途絶えてしまった。噂では、ウッドストックとコロラドの小さなコーヒー・ハウスでうたっているらしい、というニュースが流れたが、それも確かめる術がなかった。90年代に入るとカレンの情報は、まったくというほど途絶えてしまった。2000年になって、ネットからカレンの死を知ることとなった。 |
| カレン・ダルトンの本名は、カレン・J・カリカー。1937年7月19日生まれ。オクラホ州出身。アメリカの先住民、インディアンの血が流れているという。消息が途絶えたはずで1993年3月19日、ニューヨークで亡くなっていた。極度のアルコール中毒とドラッグ漬けだったようで、晩年はニューヨークでホームレスのような生活をしていたとも言われている。享年55。残念ながら生い立ちは、まだ謎だらけだ。カレンの名が語られるようになったのは、1960年代のフォーク・リヴァイヴァルからだった。この未曾有のフォーク・ブームの発信地だったのが、ニューヨークのグリニッチ・ヴィレッジ。ここには「コーヒー・ハウス」と呼ばれたライヴ・スポットが多く存在した。カレンは50年代後半からヴィレッジで高い評価を得ていた。ソウルフルなヴォーカルはカレンの圧倒的な存在感を示し、彼女の実力を最初に認めたのが、かのフレッド・ニールだった。 |
| カレンはこの頃、すでにギブソン社製の12弦ギターでうたっていた。憶測だが、カレンは、フレッド・ニールが弾く12弦ギターに触発されたのではなく、きっと黒人フォーク&ブルース歌手のレッドベリーが弾く12弦ギターに魅了され、弾き語りに使うようになったに違いない。60年代に入ると、カレンはヴィレッジとコロラドを行き来して得意のブルースで多くの音楽ファンを魅了した。特に若きボブ・ディランは、カレンの才能にぞっこんだったようで、「最高のブルース歌手だった!」と述懐している。当然、ディランやフレッド・ニールと交流があったわけで、パソコンでカレン・ダルトン、ボブ・ディラン、フレット・ニールと打ち込んで検索すると、61年2月ニューヨークのコーヒー・ハウス「カフェ・ホワ」で撮られた微笑ましい三人の記念撮影を容易に探すことができる。ぜひ観て欲しい。 |
| この記念すべきデビュー盤を仕掛けたのは、ニック・ヴェネットだった。カレンのアルバムを「ぜひ発売すべきだよ」とニックに告げたのが、フレッド・ニールだった。賢明なロック・ファンにはニックの説明が無用だが、念のために少しだけ書いておこう。1933年生まれのニックは19歳でキャピトル・レコードに入社、A&Rマン、プロデューサーとして大活躍。98年1月に亡くなっている。初期ビーチ・ボーイズ作品のプロデュースを手掛けたことで広く知られている人物。その他、グレン・キャンベル、フレッド・ニール、サミー・ウォーカー、ガスリー・トーマス、ロス・シスターズ、 ディンズモア・ペイン、リンダ・ロンシュタット、ハーツ&フラワーズなどを手掛けたことでも有名。 |
| フレッド・ニールは、先にも触れたが50年代終盤からグリニッチ・ヴィレッジのフォーク・シーンで名を馳せたミュージシャンだった。フォーク・ブルース歌手といえば、デイヴ・ヴァン・ロンクやエリック・フォン・シュミットなどが50年代後半からニューヨークで活躍しており、フレッド・ニールと人気を競っていた。だが、ブルースに対する表現は、明らかに違っていた。前者の二人は、黒人ブルースマンのようにうたうことを得意としていた。だが、フレッド・ニールはオリジナル・ソングに固執していて、独自のフォーク・ブルースを12弦ギター弾き語りで表現していた。出生作は、映画『真夜中のカウボーイ』の主題歌「うわさの男/Everybody's Talkin'」。アルバムはエレクトラ、キャピトルから発売された。フレッド・ニールはカレンのセカンド盤『In My Own Time』にコメントをこう寄せている。“カレン・ダルトンは、ぼくのいちばんお気に入りの歌手だ。初めて彼女の歌に接したのは、グリニッチ・ヴィレッジのコーヒー・ハウス「Cock And Bull」(後にこの店は、「The Bitter End」と改名、フォーク・リヴァイヴァルの発信地として名を馳せる)だった。親友のディノ・ヴァレンティとその昔、カレンのブルースに心酔したものだったよ”と。 |
| カレンは60年代初頭、個性豊かな弾き語りブルースをうたっていたにも関わらず、ニューヨークのフォーク・シーンでは高い評価を得ることができず、悩んで新しい活動場所をデンヴァーに求めることになる。流れ着いたコロラドには、ハリー・タフトが経営する「デンヴァー・フォークロア・センター」があった。フォーク愛好家の“集いの場所”として近隣から明日のフォーク・スターを目指す若者が集まっていた。この地で活躍するウォルト・コンレィと仲良しとなり、62年に発売された自主制作盤に参加、トラッド・ソング「Red Apple Juice」を録音している。同じ時期カレンは、コーヒー・ハウス「Attic」に出没して、コロラドの音楽ファンに気だるいカレン節ブルースを披露したこともあった。最近になって「Attic」のライヴ録音が見つかり、Megaphoneというインディーズから『Cotton Eyed Joe』という表題でCD化され、熱心なカレン・ファンを喜ばせてくれた。またアシッド・フォークで名を上げたホリー・モダル・ラウンダーズとも仲がよく、彼らのランダー盤『Alleged In Their Own Time』に客演している。 |
| 本盤が発売されたのは、1969年のことだった。ジャケット写真は、目を閉じながらうたう妖艶なカレンを捉えたものだった。看板の12弦ギターの弾き語りと、恐らくニューヨーク・フォークのヒーロー、ピート・シーガーに触発された観が強いヴェガ製ロングネック・バンジョーを手にしたカットを二重写しとした写真が、いまでも強いインパクトを放っている。バンジョーを手にした写真が使われていたが、残念にも本盤ではバンジョーの弾き語りを味わうことができない。カレンのワン&オンリーだった妖しいバンジョー・ブルースは、パラマウント盤『In My Own Time』でぜひ味わって欲しい。 |
| 待望の紙ジャケットで登場した本盤のプロデューサーは、いうまでもなくニック・ヴェネット。録音は、ニューヨークのレコード・プラントの「スタジオA」で行なわれた。バック・ミュージシャンは、ベースにボブ・ディラン人脈で広く知られているハーヴィー・ブルックス、パーカッションにはニューヨークの売れっ子ドラマー、ゲイリー・チェスター、エレキ・ギターにキム・キング、アコースティック・ギターにダン・ハンキンがクレジットされている。ちなみにこの録音でカレンの歌唱に惚れ込んだハーヴィー・ブルックスは、パラマウント盤『In My Own Time』のプロデューサー役を名乗りあげたという。本盤での聴きどころは、何といってもしゃがれ声で一成を風靡した女性ジャズ歌手、ビリー・ホリデイを彷彿させる“スモーキー・ヴォーカル”といってよいだろう。サウンドは独特のブルース・グルーヴ、心にしみるカレンのヴォーカル、どれをとっても本作収録トラックはすべて秀作。全体的に浮遊感あふれるフォーク・ブルース作品。こうした観点から“アシッド・フォークの傑作”と言っても良いかも知れない。 |
| 01. Little Bit Of Rain カレンの才能をいち早く見抜いたフレッド・ニールの代表的作品のカヴァー。不気味なハーヴィーのベース・ソロ。そしてカレンの気だるいブルース・ヴォーカルが聴こえてくる。もうこの1曲で彼女の虜(とりこ)になってしまう。原曲は、ニールの1965年発売のエレクトラ盤『Bleecker & MacDougal』に収録されている |
| 02. Sweet Substitute 12弦ギターの弾き語りが存分に味わえる作品。素材は、ニューオリンズ出身の偉大なジャズ・ピアニスト、作曲家ジェリー・ロール・モートンの書いたものだ。ビリー・ホリデイの物憂げなブルース・ヴォーカルをイメージさせる絶品の歌唱だ! |
| 03. Ribbon Bow ファルセットでうたうアメリカン・トラッド歌手、ボブ・ディランも尊敬したジョン・ジェイコブ・ナイルズのレパートリーを大胆にブルースにアレンジした録音。ここからフォーク・リヴァイヴァルの洗礼を受けた若者だったことが伝わってくる。それにしても見事なアレンジだ。 |
| 04. I Love You More Than Words Can Sayd カレンの素晴らしい選曲のセンスを物語るトラック。何を隠そうソウルの王者、「Dog Of The Baby」のヒットでお馴染みのオーティス・レディングの1967年録音カヴァー。ここでもハスキー・ヴォーカルが冴え渡っている。 |
| 05. In The Evening 憶測だが、かなり影響を受けたに違いない黒人フォーク&ブルース歌手、レッドベリーの十八番作品としても広く知られている。カレンに少なからず影響を与えたロング・ネック・バンジョーの弾き語りのピート・シーガーの録音もあった。力強いレッドベリーのギター演奏と違って、どうやらフレッド・ニールが弾く緩い12弦ギター演奏に近い。 |
| 06. Blues On The Ceiling 2作目のフレッド・ニールのカヴァー。オリジナルは、エレクトラから発売されたニールの『Bleecker & MacDougal』に収録。この盤は、英国でベスト・セラーを記録した。カレンは、英国人と同様によほどこのアルバムがお気に入りだったのだろう。 |
| 07. It Hurts Me Too ここでも抜群の選曲センスを窺わせてくれる。ミシシッピ出身の偉大なブルース歌手、エルモア・ジェイムズの代表作カヴァー。ジェイムズはスライド・ギターの達人で、アメリカン・ロックのギタリストに大きな影響を与えたことでも知られている。 |
| 08. How Did The Feeling Feel To You グリニッチ・ヴィレッジのフォーク・シーンで異才を放ったティム・ハーディンが書いたものだ。ティム・ハーディンは、フォークとジャズを融合させた独特の存在感を放ったフォーク歌手だった。カレンは、きっとグリニッチ・ヴィレッジ時代に交流があったに違いない。 |
| 09. Right, Wrong Or Ready 無名の黒人フォーク歌手、メイジャー・ウィリーの作品カヴァー。メイジャー・ウィリーは50年代の終盤からワシントン広場のフォーク・ジャムで活躍したこともあった。が、いつしかその名は忘れられてしまった。フォークウェイズ盤の『Folk Music Of Washington Square』に1曲だけメイジャー・ウィリーの弾き語りを聴くことができる。 |
| 10. Down On The Street 先にも触れた黒人フォーク&ブルース歌手、レッドベリーがうたった渋いブルースのカヴァー。余談だが。レッドベリーの「おやすみアイリーン / Goodnight Irene」をロック・シーンで有名にした男は、ライヴやアルバムでお馴染みのライ・クーダーだった。 |
| (2009年3月加筆) |
| 一覧に戻る | トップに戻る |