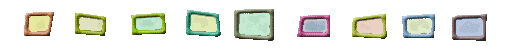
墓場まで何マイル?
〜2003年10月の寺山修司〜
2003年10月、どういうわけか1週間のうちに立て続けに3本の寺山公演が行われた。
以下の写真と文章は、そのレポートです
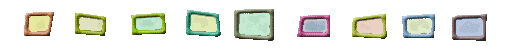
墓場まで何マイル?
〜2003年10月の寺山修司〜
2003年10月、どういうわけか1週間のうちに立て続けに3本の寺山公演が行われた。
以下の写真と文章は、そのレポートです
第1章 墓場まで何マイル?〜10月9日in日暮里・本行寺〜
2003年9月、月刊テラヤマ新聞から素敵なチラシが届いた。
crosstalkなる制作集団とテラヤマ新聞が共同して、「墓場まで何マイル」と題したイベントを行うというのである。
しかも何故か、お寺で。寺山マニアを自称する身としては、こんな面白い催しに行かないわけにはいかない。
場所は日暮里駅前本行寺、時刻は夕刻6時過ぎ。空には満月から少し欠けたお月様ぽっかりと浮かんでいる。
門前には受付案内の黒板、そして掲示板の端っこの方にも、申し訳なさげにチラシが貼ってある。
いまだ扉の開かぬ本堂の前には、集まった寺山ファンが待ちきれぬようにたむろしていた。
「ああ、なんだか、本当に寺山さんが好きな人たちが、集まってきてるんだなあ」としんみり。
予約をしていたので、さっそく受付で名前を告げる。
と、「あ、テラヤマ新聞を読んでくださってる○○(本名)さんですよね。」と名前を覚えられていて、びびる、
(いや、もちろん嬉しかったのですが……)
開場まで間があったので、お寺の中を散策。竹林の中に小林一茶の歌碑が建っていたりと、なかないい雰囲気。
そして18時半になり、開場。お馴染みのチラシが張られた扉が開く。
ドリンクチケットとして渡されていた花札(何故?)で、さっそくワインをもらう。
本堂の中には、薄黄色のあかりに照らされて、無数の展示物が置かれていた。
先ず目を引いたのは、チラシのイラストも描いた綺朔ちいこの絵。
会場のそこかしこにさりげなく飾ってある。どれも妖しく美しい、素晴らしい作品ばかり。
月並みな発想だが、
「少女と人形と娼婦とは、本来同じものである。それは内密の無限性の迷路であり、世界遊戯の対象なのだ」
という寺山修司の言葉を思い出した。
そして清水真理制作の少女人形。生で観たのはスズナリの「闇夜幻燈逆説華祭」以来。
中野タコシェで、彼女のポスカードを見つけるたびに買い漁るのを、実は密かな楽しみにしている。
背後の幕には山田勇男の絵が飾ってあった。
本殿には小さな寺山人形とお焼香が設置されていた。
「どうぞお焼香していってください」の声に誘われ、観客は次々とお焼香し、手を合わせていった。
「ああ、みんな本当に寺山修司が好きな人たちばかりなんだなあ」と嬉しくなる。
やがて19時となり、観客は畳に並べられた座布団に着席。公演が始まった。
1番手はホフマン+モンドリアンの「9 OCT.03,thu.」。
閉じたふすまの向うに浮かび上がる少女の影。生身の人間を使った等身大影絵遊びと言葉遊び。
絵的な美しさに対して、言葉の威力が弱かったように思う。
「私は私、あなたじゃない」って、それじゃあ「エヴァンゲリオン」じゃん。
2番手はふすまをスクリーンにした、田中未知監督、寺山修司出演の短編映画「質問」の上映。
生身の出演者の方々には申し訳ないが、正直、これが一番面白かった。やっぱ寺山は別格、天才だ。
「”希望”という言葉は何故二文字なのでしょうか?」
「”幻滅”って言葉2文字だから、やっぱそれより多すぎちゃいけないってことなんじゃないかな」
「世界中の人間が同じ名前を持つとしたら、どんな名前がいいと思いますか?」
「”名前”って名前でいいんじゃない。そもそも名前っていうのは他の人間と区別するためにつけるものだから、
みんな同じ名前だったらつける必要がないんだよね。それでもつけるなら、”名前”でいいんじゃないかと」
「目を瞑ったまま何歩くらい真っ直ぐ歩けますか?」
「一歩も歩けないね。目を開けてても、あっちへふらふら、こっちへふらふらで、真っ直ぐ歩くことがないからね」
という風な、寺山のユーモアの効いた当意即妙な返答に、客席からは笑いが上がっていた。
3番手は天井桟敷のメンバーだった稲葉憲仁の朗読による「永山則夫への70行」。
「おれのどこかに二十歳がある」というフレーズが印象的な詩で、CDにも収録されている。
読み終わった原稿を一枚一枚散らしていく演出が、単純だがかっこいい。
4番手は3人の出演者による舞踏風パフォーマンスの「蜃気楼」。
赤縄で縛られた学制服の男。シンバルを叩いてシャボン玉を割ろうとする男。
そして大きく膨れた白いドレスを纏い、それを脱ぎ去ろうともがく女。
その様はさながら、卵の殻から抜け出ようともがく、生まれたばかりの白蛇のようだった。
5番手はテラヤマ新聞編集の金子千絵による、「日本自殺考」の朗読。
綺朔ちいこの絵の前での立ち姿は、まるで絵の中の少女が抜け出てきたかのような印象。
が、ここで折り悪く、本来終演予定の時間だった20時半になってしまった。
少女的な切ない声でなかなかよかったのに、席を立つ人が出て客席がざわざわし、印象が薄れてしまったのが残念。
6番手は天舞艦主宰の市川正による「庸」。
僧正の衣装を覆った男が、外から現れてゆっくりと本堂へと入ってくるという、言葉にするとただそれだけの舞踏だが、
夜のお寺で見ると抗いがたい不気味な迫力がある。
そして最後は綺麗な着物を着た小学生くらいの女の子、ぼたんによる「懐かしの我が家」の朗読。
たどたどしい声で読んでいく様がなかなか微笑ましかった。愛嬌愛嬌。
正直「作品公演」として見れば物足りなかったところもあるが、独特の雰囲気は十分に楽しませてもらった。
crosstalkの目的は「場」を創ることにあるそうだから、その意味では大成功だったと言えよう。
また次があることを期待しながら、私は門をくぐって家路に着いた。
第2章 田園に死す〜10月12日in松本市・ピカデリーホール〜
中央線の電車に揺らリ揺られて降り立った松本駅。
いつもは北アルプスへのアプローチとして使っているが、今日は違う。
演劇実験室・経帷子(きょうかたびら)の公演、寺山修司原作「田園に死す」を観劇するためである。
駅から十数分歩いたところに、昔ながらの懐かしい街並を再現した縄手通りがある。
夏にはここで経帷子による市街劇が行われたそうである。
縄手通りをすぎた所に、松本ピカデリーホールはあった。昔ながらの小さな映画館・劇場といった感じのところだ。
パチンコの周りにあるような、少し安っぽい感じののぼりがたくさん立っている。
サーカスの雰囲気にグリコのキャラメルのキャラクターを絡ませた感じの、派手なチラシも飾られている。
チケットも同様。「村にサーカスがやってきた」という感じだ。
そして開演。オリジナルの音楽に乗せた「こどもぼさつ」がなかなかいい出来だ。
舞台づくりの雰囲気もいいが、どうも役者や演出の層が薄い感じがする。
地方劇団はみなそうかもしれないが、一言で言えば、人手が足りない。
ここでもう少し俳優が出てくれば、ここでこの小道具があればもっとよくなるに、というところが多々見受けられた。
サーカス一座のシーンが、団長によって語られるだけで、実際のサーカスの人々が出てこないのはいかにも寂しい。
また、少年が駆け落ちする人妻とサーカスの空気女の役柄を一人のキャラクターにまとめ、
その部分のストーリーをオリジナル脚本で補っているのだが、寺山脚本に対して明らかに言葉の力が足りない。
物語中に挿入されるアニメーション風に処理された映像や、オリジナルの音楽のセンスは非常によかった。
あとはそれに拮抗するだけの力(と人数)を生身の役者が持てれば、もっといい作品が出来るだろう。
最後は、最近やたらとはやってる感じがする、「邪宗門」のラストシーン風の劇的言語による終幕。
舞台崩しの後、役者が好き勝手にしゃべり始めるという奴である。
それまでのストーリー展開となんら繋がりがないので、とっ散らかって終わってしまった感じは否めない。
何だかんだ言って、少ない役者で非常によく頑張っていたのではないかと思う。
正直、地方劇団ということでもっとひどいものを想像していたが、なかなどうしてアングラな空間を作り上げていた。
機会があればまた観てみたいと思う。
松本駅の上に広がるバニラ・スカイを見上げながら、帰りの汽車に乗り込んだ。
第3章 われに五月を〜10月16日in港区赤坂・草月ホール〜
10月の寺山修司関連作品の連続公演もいよいよ大詰め。
トリを飾るのは、フォア・レディース・シリーズでお馴染みの宇野亜喜良が芸術監督を務めるダンス・エレマンの公演、「われに五月を」である。
ダンス・エレマンのHPからのチケット購入に限って、宇野亜喜良デザインの4枚組チケットを手に入れることが出来た。
4枚ともため息が出るほど美しいデザインで、栞として使ってみても楽しい。当日の公演会場でも、300円で販売されていた。
さて、新宿駅から地中深くに沈んでいる都営大江戸線に乗り込み、約7分。
青山一丁目駅から歩いて数分の場所に草月ホールはある。ロビーで待っている観客には、若い女性の姿が多い。
当然ながら客席内は撮影禁止なので、ロビーに飾られていたポスターを撮影。
過去の公演ポスターや人形、写真など、様々なものが展示されていて、待ち時間も飽きない。
そして上演開始だが、何故10月の公演なのに「われに五月を」というタイトルなのかとか、
タイトルでそう謳っときながら、劇中で朗読される短歌は「田園に死す」の短歌ばっかじゃねえかとか、
寺山修司マニアとしては突っ込みどころがいくつかあった。
内容は"Alice in wonderland"というか、寺山の不思議世界に迷い込んでしまった少女の夢という感じ。
宇野亜喜良の絵からのそのまま飛び出してきたような美粧の少女たちが舞い踊る。
肌の露出は少ないにもかかわらず、非常にエロティックな感じがした。
何がエロティックなのかというと、それは艶かしいほど繊細に動く少女の表情や指先や爪先で、それがつまり「ダンス」の魔力なのだろう。
10月9日の項で引用した寺山修司の言葉は、たしかこんな風に続けられていた。
「僕は年をとったら、人形と一緒に暮らしたい。
歌ったり、浴槽に入ったり、ホフマンの童話を読んだり、レスボスの果実を貪ったり、僕の肩を揉んでくれたりする、自動人形たち、沢山と。
僕は人形となら、うまくやっていけそうだ。
だが、僕が暮らす人形たちは、セルロイドや蝋細工では駄目だ。
キャロルの写真集に出てくるような、血の通った生き人形でなければ」
ほら、寺山さん、あなたの欲しがっていた少女人形たちが今ここにいるよ。ほら、捕まえないと。
2時間の上演時間はあっという間にすぎていった。
部屋に貼ったポスターを眺めながら、独り悦に入る。
楽しい1ヶ月をありがとう。
![]()