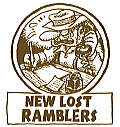 |
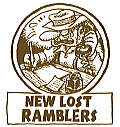 |
| ■ NEW LOST RAMBLERS |
| ■ 2007年3月13日(火) |
Gram Parsons『GP』 |
| 曲目 | |
 |
01. Still Feeling Blue 02. We'll Sweep Out The Ashes In The Morning 03. A Song For You 04. Street Of Baltimore 05. She 06. That's All It Took 07. The New Soft Shoe 08. Kiss The Children 09. Cry One More Time 10. How Much I've Lied 11. Big Mouth Blues |
| ♪グラム・パーソンズは、ザ・バーズ、ザ・フライング・ブリトウ・ブラザースなどでお馴染みの“カントリー・ロック”ブーム推進役を務めた重要な人物だ。その後、ソロ・ミュージシャンに転じて、ロンサムなホワイトブルースを漂わせるアルバムを発表、ロック・ファンの心を捉えた。本盤は、ソロ活動の第1弾。1973年リプリーズより発売されたものだ。カントリー・ロックの歴史から外せない作品として高く評価されている。エルヴィス・プレスリーのバックでお馴染みのギター名手ジェイムズ・バートン、盟友女性カントリーのヒロイン、エミルウ・ハリス、ナッシュヴィル・カントリーの大物スティール・ギター奏者、バディ・エモンズ、その他の一流ミュージシャンのサポートも、アルバム作りの完成度の高さを示している。録音は、1972年9月と10月に行われた。パーソンズの録音は、1990年代にシアトル、シカゴ、テキサスで沸き起こった“オルタナ・カントリー”にも大きな影響を与えたことでも広く知られている。内省的で深く味わいのある個性的なヴォーカル、そのヴォーカルと白人ブルース=ブルー・カントリーとも解釈できるサウンド志向が、オルタナ・カントリー・ミュージシャンに深い感銘を与えたに違いない。 |
| グラム・パーソンズは、フロリダ州ウィンターヘヴン出身。1946年生まれ。日本流にいえば、昭和21年生まれだ。どうやら実家はかなりのお金持ちだったようで、フロリダ特産のオレンジ果樹園を経営していたという。幼い頃の音楽環境といえば、ご多分にもれず上流階級によく見られるピアノと絡んでいた。クラシック・ピアノのレッスンを両親から強要されていたようだ。だが、反抗期の少年時代を迎えてからロックンロールの虜となっていった。そこにはあのエルヴィス・プレスリーの影が見え隠れしていた。地元でエルヴィスのライヴを観て感動、またロック狂に友達からの刺激も受けてギターを手にした。 |
| ロックンロールへの病が高じて、高校時代にバンド“ザ・ペイサイダーズ”、“ザ・リジェンツ”を結成した。バンド活動に生き甲斐を見つけて、将来プロの道を歩む決心が芽生え始めた。ところがアメリカン・ポップス・シーンが予期せぬ方向を示し始める。ロカビリー、ロックンロールの寵児だったエルヴィス、チャック・ベリー、その他の人気が衰えて、ロッカバラードと呼ばれる新しいティーン・ポップス(ポール・アンカ、ニール・セダカに代表される)が流行り始めた。ロックンロールのソフト化だった。この減少もつかの間で、今度は、ニューヨークを発信地とするフォーク・リヴァイヴァルが生まれた。 50年代半ばにザ・ウィーヴァーズというコーラス・グループが「おやすみアイリーン」を大ヒットさせ、これに続いたのがザ・タリアーズの「バナナ・ボート・ソング」、ザ・キングストン・トリオの「トム・ドゥーリー」、ブラザース・フォアの「グリーンスリーヴス」だった。全米は、モダン・フォーク・コーラスのヒット曲に一喜一憂した。60年代初頭には、ついにスパー・スター、ピーター・ポール&マリーが誕生した。パーソンズや周囲の友人たちもモダン・フォークに影響されて、コーラス・グルームを結成知ることを画策した。そこで誕生したのが、キングストン・トリオっぽいモダン・フォーク・グループ“ザ・シャイロ”(このグループの録音は、70年代にアルバム化されて、パーソンズ・フリークを喜ばしたこともあった)だった。大学は名門ハーヴァードを選んだ。入学した頃はフォーク・ブームの全盛で、キャンパス・シーンは、フォークに夢中な学生が溢れていた。高校時代に母を亡くしたパーソンズは、大学生活でもその悲しみを引きずってしまい、逃れるように音楽にのめり込んでいった。大学生活でジョン・ニュースという男と知り合ってから、パーソンズの音楽志向は一変してしまう。 |
| ニューヨークでの音楽三昧を続いたが、今度は彼のおかげでカントリー・ミュージックに興味を抱くようになる。ロック・テイスト満点のマール・ハガード、ローズ・マドックス、バック・オウエンスに代表される西のカントリー、ベイカーカーズ・フィールド・サウンドを聴きようになっていった。フォークからカントリーへの興味は、思わぬ結果を招いた。ジョン・ニュースとバンドを立ち上げる決心をした。狙いは単なるコピー・バンドに終わらないオリジナリティーを持ったバンドだった。グループ名は、インターナショナル・サブマリンバンド(以下ISBと略す)。 |
| ISBの活動拠点は、ニューヨークからロサンゼルスへと移された。1967年、チャンスが訪れた。著名な音楽プロデューサー、リー・ヘイゼルウッドが気にいってくれ、アルバムを作らないか?と誘ってくれた。プロへの道が本格的に始まった。LHIというインディーズから念願のデビュー・アルバムが発売された。表題は、『セイフ・アット・ホーム』。だが、アルバムの売れ行きは散々だった。このまま無名ミュージシャンで終わりかと危惧したが、天が味方した。パーソンズの才能は、マネージャーを通じてザ・バーズ関係者に伝わり、メンバー唯一のカントリー好きクリス・ヒルマンと親交を持つようになる。この縁で運命は急展開した。栄光のザ・バーズのメンバーにスカウトされる。カントリー・ロック不滅の名盤と呼ばれている『ロデオの恋人』作りに参加した。そのアルバムは、ナッシュヴィルで録音され、変則レコーディングを行った。つまりパーソンズのリード・ヴォーカルと、ロジャー・マッギンのリード・ヴォーカルが録音された。その結果採用されたたのが、マッギン・ヴァージョンだった。確執が始まった。これが引き金ではないが、パーソンズはザ・バーズを去り、新しいカントリー・ロック・バンド“フライング・ブリトウ・ブラザース(以下FBBと略)”を結成、押しも押されもせぬスターの座を歩み始める。 |
| FBBは、カントリー・ロック・ブームをザ・バーズより高い位置で推し進め、ロック・ファンにカントリーの魅力を植えてくれた。A&Mレコードに遺したFBBのアルバムは、アメリカン・ポップスを語る上でも忘れてはならないだろう。ところがこの時期にパーソンズは、何かに憑かれたように悩み始める。バンドは解散に憂き目に…。ドラッグとアルコール漬けにはまって行く(これが災いとなり26歳の若さで亡くなる)。エミルウ・ハリス、ローリング・ストーンズなどが、こうした状況の中でもパーソンズの才能を応援してくれた。1972年、リプリーズからソロ・アルバム作りの依頼が舞い込んだ。いまお手元にあるCDがそれに当たる。 |
| アルバム作りに参加した主なミュージシャンを紹介しておこう。チキン・ピッキング・ギターの名手ジェイムズ・バートンは、リード・ギターを担当。ペダル・スティール・ギターは、ナッシュヴィルの大物スタジオ・ミュージシャン、バディ・エモンズ、バンジョーは、ブルーグラス・ロックで名を馳せた才人カントリー・ガゼットでお馴染みのアラン・マンデ。ピアノはエルヴィス・バックで有名なグレン・ハーディン、ドラムスは、好漢ロニー・タット、紅一点エミルウ・ハリスのヴォーカル参加も嬉しい。 |
| 01. Still Feeling Blue 失恋ソング。だが、サウンドは軽快。カントリー・ロックの道しるべを示している傑作だ!カントリーの楽器(フィドル、ドブロ、バンジョー、スティール・ギター)の魅力を余すことなく伝えている。FBB伝統のロック魂を継承した素晴らしい作品。 |
| 02. We'll Sweep Out The Ashes In The Morning 典型的なベイカーズ・フィールド・カントリー。ここでも恋人たちの“愛”の苦しさを唄っている。スティール・ギターとドブロ・ギターのサポートも捨て難い。エミルウ・ハリス参加で、いっそうの切なさが漂っている。 |
| 03. A Song For You アシッド・フォークの雰囲気が伝わる傑作。このシーンの雄、フレッド・ニールのキャピトル録音にも通じる。ニューヨーク・フォーク・シーンの体験者ならではの新しいカントリー。エミルウとの淋しげなデュオも心憎い演出だ。 |
| 04. Street Of Baltimore カントリーやフォーク・シーンでお馴染みの放浪者を題材としたものだ。「ジェントル・オブ・マインド」のヒットで広く知られているグレン・キャンベルの作風を何故かイメージさせてくれる。 |
| 05. She 本盤のハイライト・トラックといってもいいだろう。泣きのパーソンズ節がじっくりと味わえる名作だ。苦難の道を歩む少女(彼女)を、「唄うこともできた。ハレルヤ…」と叫んでいるのが印象的。やはりパーソンズの哀愁を帯びた切ないヴォーカルが最大の聴きどころだろう。見方をかえれば、孤高の白人ブルース作品といってもいい。 |
| 06. That's All It Took 再び若き日のパーソンズが惚れたカントリー、ベイカーズ・フィールド・サウンドを彷彿させる作品。このシーンの大物、バック・オウエンスのサウンドに近い。ちなみにベイカーズ・フィールドという町は、「ナッシュヴィル・ウェスト」と呼ばれた。 |
| 07. The New Soft Shoe パーソンズの書き下ろし。「新しい靴」にまつわる物語ソング。ここではチェット・アトキンスが考案したソフト・カントリー「ナッシュヴィル・サウンド」の手法が施されている。 |
| 08. Kiss The Children 典型的なホンキー・トンク・カントリー。ジェイムズ・バートンの小粋なギター芸「チキン・ピッキング」がたっぷり味わえる。パーソンズのレイジーで、ブルーなヴォーカルは、いうまでもなくここでも最大に発揮されている。 |
| 09. Cry One More Time 珍しくブラック・ミュージックのノリだ!R&Bアレンジの妙は、FBB時代にも良く聴けたものだ。ここでもジェイムズ・バートンのギターが聴きどころ。 |
| 10. How Much I've Lied エルヴィス・コステロのカヴァーでロック・ファンに広く知られている作品。ここでもロッキン・カントリー、ベイカーズ・フィールド・サウンドの主役だったバック・オウエンス、マール・ハガードなどの作品をイメージさせる。 |
| 11. Big Mouth Blues カントリー・サウンドに黒人のR&Bビートを織り込んだ意欲的な作品。FBBでもお馴染みの手法だ。このあたりがもうひとつのグラム・パーソンズ流カントリー・ロックの魅力といえそうだ。 |
| (2003年 / 2007年2月加筆) |
| 一覧に戻る | トップに戻る |