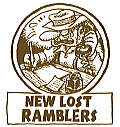 |
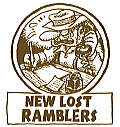 |
| ■ NEW LOST RAMBLERS |
| ■ 2006年10月4日(水) |
Bob Dylan 『Modern Times』 |
| 曲目 | |
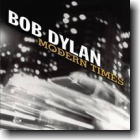 |
01. Thumder On the Mountain 02. Spirit On The Water 03. Rollin' Tumblin' 04. When The Deal Goes Down 05. Someday Baby 06. Working's Blues#2 07. Beyond The Horizon 08. Nettie Moore 09. The Lever's Gonna Break 10. Ain't Talkin' |
| ♪何かと話題の多いボブ・ディラン。最近では米週刊誌「Time」で、“20世紀の200人”に選ばれたディラン。勢いづいたのか、自らの企画・脚本で映画作りにも手腕を発揮した。題名は『ボブ・ディランの頭のなか』。ライヴ・シーンも観られ、話題を呼んだ。ディランが演じた男の名前は、ジャック・フェイトだった。お気づきだと思うが本作のプロデューサー名は、ジャック・フロストとクレジットされている。ディランは、ここでは映画の役名(ジャック・フェイト)と似通ったプロデューサー名に使っている。ディラン一流のジョークなのだろう。だが、本盤のプロデュースは、ジャック名義のボブ・ディラン。つまりディランのセルフ・プロデュース作品なのだ。この点は、このアルバムを理解する上でかなり重要だ。映画の内容は、近未来の独裁国家を強烈に皮肉ったものだった。この映画でディランは、国が必ず迎える戦争と平和問題、終焉期などを模索したに違いない。ということで、『モダン・タイムズ』は、微妙に映画『ボブ・ディランの頭のなか』とリンクする内容を帯びた作品といってもあながち大袈裟ではあるまい。 |
| ディランのツアー好きは有名だ。1970年代の「ネヴァー・エンディング・ツアー」は、彼の音学歴を辿る上でも外せない。では、なぜディランは、コースト・トゥ・コースト(全米)・ツアーを行うのだろう。答えは、「唄は継がれてうたわれてこそ素晴らしい」と公言しているからだ。この考えはレコード、CDなどより、ライヴこそ伝わると信じているからだろう。こうした感覚の源泉は、師でもあるウディ・ガスリー、兄貴的存在だったランブリング・ジャック・エリオットなどの精神を受け継いだものだ。過酷なツアーを65歳で迎えても行う理由はまだある。 |
| 素人芸だったアメリカ伝統音楽(トラディショナル・フォーク・ミュージック)は、やがてレコード発明とぶつかり商業音楽として生まれ変り、ブルース、ゴスペル、ヒルビリー、オールド・タイム・ストリング・バンド、ジャグ・バンド、その他、アメリカ音楽の根幹を支える様々なジャンルが誕生した。1920年代から30年代の歌手、バンドたちはレコード発表、ラジオ出演の傍ら精力的にツアーを行った。その殆どは、ディランのように大衆と直に接することができるライヴ・ツアーを好んだ。こうした背景から40年代になると、コースト・トゥ・ツアーが盛んとなっていく。なかでもディランが尊敬するブルーグラスの父、ビル・モンロー、50年代カントリー・スター、ハンク・ウィリアムズなどは、「テント・ショウ」と称して全米の小さな町々を訪れ、カントリー・ミュージックの楽しさを植えつけ始めた。もちろん多くのミュージシャンが出演した。ディランのネヴァー・エンディング・ツアーのルーツは、この辺りが求めるのが的確だろう。ディラン・ツアーは、前座にルーツ系ミュージシャンを置くことが多い。ここにもテント・ショウの面影がうかがえる。 |
| 前置きはこのくらいにして、この新作に触れてみよう。『モダン・タイムズ』は、ディランがほれ込んだハリー・スミス編纂『アンソロジー・オブ・アメリカン・フォーク・ミュージック』(フォークウェイズ盤)や、ディランとザ・バンドのウッドストック・セッション(レコードは、『地下室』で味わえる)などをかなりイメージさせてくれる。つまりディランはアメリカン・ルーツとして近年注目されているポピュラー音楽の源、ジャズ、カントリー、ブルースなどをブレンドした音楽に重きを向けた観が強い。フォークやロックなどに体をゆだねるのではなく、音楽の幅を楽しみながらゆっくりと反応し始めている。こうした志向は、ディランが最近始めたラジオDJ番組からもよく理解できる。それは、アメリカの衛星ラジオ「MX・サテライト・ラジオ」の“ディープ・アルバム・ロック・チャンネル”で聴くことができる。2006年3月からスタート。ディラン自らが選曲する大好きなアメリカン・ミュージックの1時間音楽番組だ。またディランが自由奔放にアメリカ音楽を楽しみ始めたのは、ツアーで前座を務めたエイモス・リー、マール・ハガード、ウィリー・ネルソン、ホット・クラブ・オブ・カウタウンなどとの交流から生まれたといってもいいだろう。 |
| アルバム的には、もうひとつの捉え方ができる。本盤は、20世紀最後の作品『タイム・アウト・オブ・マインド』、ダニエル・ラノワのプロデュース作品『ラヴ・アンド・セフト』の延長上に位置するといってもいいだろう。ディランをフォローするミュージシャンも注目したい。まずドニー・へロンの存在だ。ヴァイオリン、マンドリン、スティール・ギターなどが巧みで、カントリー・ロック・バンド「BR549」のメンバーとしても広く知られた人物だ。ベースのトニー・ガーニエは、ネオ・ロカビリーの帝王と異名を取ったロバート・ゴードンの録音でも手腕を発揮したミュージシャン。マーシャル・クレンショウ、ブライアン・セッツアーなどの録音にも参加している。ギターのデニー・フリーマンは、テキサス・シーンで著名なミュージシャン。モダン・ブルースでお馴染みのジミー&スティーヴィー・ヴォーン兄弟との交流は有名だ。またタジ・マハールのバックを務めたこともある。もうひとりのギタリスト、スチュ・キンボールは、ボストン地区で名を馳せたスタジオ・ミュージシャン。ディランのアルバム『エンパイア・バーレスク』の録音に参加、2004年からディランのツアーに起用された男だ。ドラムスのジョージ・リセリは、ニューオーリンズ生まれ。ここ数年、ディラン・ロックの要役をこなしている。ディランのレコーディングでもお馴染みだ。 |
| ★ジャケット写真について少し触れておこう。この写真は、“都会の夜の幻想”を撮り続けた写真家として有名なテッド・クローナー(Ted Croner)氏が、1947年に発表した写真集『Taxi New York At Night』から著作許可を取って使ったものだ。クローナー氏は、モノクロ写真にこだわりをもったカメラマンとしても広く知られている。残念ながら『モダン・タイムズ』の表紙を飾った写真は、少しトリミングがなされている。こうした懸念を抱いたのか、本盤のアナログ盤発売(2枚組)の中袋には、オリジナル写真がトリミングなしに掲載されている。恐らくディランは、ニューヨーク・フォーク・シーンからデビューを飾ったので、NYの夜景が気に入ったのでは…。『ディラン自伝』本の表紙を飾ったタイムズ・スクエアのモノクロ写真もニューヨークだった。ウディ・ガスリーを慕ってニューヨークに辿り着き、この地のコーヒー・ハウス「カフェ・レナ」からフォーク歌手としてデビューを飾ったディランは、歳を重ねてもニューヨークに対しての恩義は忘れないようだ。 |
| 01. Thumder On the Mountain シカゴ・ブルースとロカビリーを見事にミクスチャーした作品。ディランR&B、もしくはディラン・ロックンロールと命名してもいいだろう。曲間にチャック・ベリーのようなギター・リフが次々と登場。サービス精神満点だ。 |
| 02. Spirit On The Water アコースティック・ジャズ・アプローチが嬉しい。きっと大好きだったフランク・シナトラ、ディーン・マーティンなどのヒット曲を懐かしみながら録音したに違いない。後半のアコーディオンっぽいハーモニカと、ジャジーなギターとの絡みは、もう「アコースティック・スウィング」の世界といえそうだ。 |
| 03. Rollin' Tumblin' いきなりスライドー・ギターが炸裂するディラン流ロックンロール。ネオ・ロカビリーのロバート・ゴードン&ワイルド・キャッツが、リンク・レイと一緒に録音した作品が目に浮かぶ。ともかくカッコいい作品だ。そういえば本盤のベーシスト、トニー・ガーニエは、ゴードンと一緒のレコーディングも体験している。 |
| 04. When The Deal Goes Down ディランはここでもジャズっぽい曲を唄ってくれる。和らぐワルツにのって、艶やかなヴォーカルが味わえる。まるで1940年代にジャズ・ヴォーカル・シーンで一世を風靡した癒し系ジャズ歌手、ジーン・オースティン(代表作は、「マイ・ブルー・ヘヴン」)が唄っているようだ。ここでもディランのアメリカン・ミュージックに対する愛情がひしひしと伝わってくる。 |
| 05. Someday Baby この作品も、マディ・ウォーターズお得意のシカゴ・ブルースを下敷きにしている。サウンドは、本作でも顕著なロカビリーっぽいものだ。ウォーターズのシカゴ・ブルースと、エルヴィスのサン録音ロカビリーをブレンドしたものだから「シカビリー」と命名してもいいだろう。 |
| 06. Working's Blues#2 1960年代、西海岸を席巻したロッキン・カントリーを騒がせたマール・ハガートの作品に触発された曲。ジョニー・キャッシュもこうしたタイトルの作品を発表している。労働者の哀歌といった内容で、ウディ・ガスリーの精神が詩のなかに宿っている。コーラス部分で「この労働者のブルースをちょっとばかり唄おうよ!」と自戒を込めて唄っているのが印象的。 |
| 07. Beyond The Horizon ペダル・スティール・ギターが聴こえるカントリー・ジャズ。ハワイアン風ともいえるかも…。ウィリー・ネルソンとのツアーでこうしたサウンドをディランは習得したに違いない。哀愁をおびたディラン・ラヴ・ソングの新境地。あえてチェンジャーを使用しないスティール・ギターは、1940年代に栄えたラップ・スティール・ギターの再現を試みている。ここからもディランの素晴らしいセンスが伺える。 |
| 08. Nettie Moore ポール・クレイトンやエド・マッカーディがよくニューヨークのコーヒー・ハウスでうたったトラディショナル・ソングを下敷きとしたのだろ。やがて静かにしのびよる世界の終焉を匂わせながら唄われる、壮大で不気味なバラッドは、7分弱にも及ぶ。 |
| 09. The Lever's Gonna Break これはストレートなロカビリー・サウンド。黒人ブルース歌手、メンフィス・ミニーの作品カヴァー。エルヴィスがアーサー・クリューダップの「That's All Right」や、ジュニア・パーカーの「Mystery Train」をサン・レコードでロカビリーにアレンジして大成功を収めたように、ディランもお気に入りのブルースを、ロカビリー仕立ての作品を夢見て発表したに違いない。 |
| 10. Ain't Talkin' ラストは8分あまりの大作。おそらくこの作品がディランの新しいメッセージだろう。資本主義国家の終焉を予告するような不気味なトラック。メロディーは、戦前コモンストック(共有財産)として南部黒人・白人たちに唄われたブルースをいただいている。 |
| (2006年9月書き下ろし) |
| 一覧に戻る | トップに戻る |