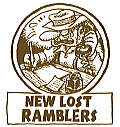 |
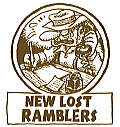 |
| ■ NEW LOST RAMBLERS |
| ■ 2004年1月26日(月) |
スティーヴ・ヤング『ロック・ソルト&ネイルズ』 |
 |
曲目 |
| 01. That's How Strong My Love Is 02. Rock Salt & Nails 03. I'm One Woman Man 04. Coyote 05. Gonna Find Me a Bluebird 06. Love In My Time 07. Seven Bridges Road 08. Kenny's Song 09. Holler In The Swamp 10. Hoboin' 11. My Sweet Love Ain't Around |
| スティーヴ・ヤングは、謎多き人物だ。生まれは南部アラバマ。あるいはジョージアとも言われている。生年月日すら不明だ。一説によると、1940年代半ばに生まれたという。ヤングは、そうすると現在はもう60歳を迎えた年齢なのだろうか?このアルバムは、1969年発売された。その時のヤングの年齢は、20歳を超えていたに違いない。 |
| 彼は過去、シンガー・ソングライターとか、カントリー・ロック・シンガーとか、スワンプ・ロッカーなどと様々なジャンルで語られてきた。が、いったいその正体は何だったのだろう。辿った道を少し探ってみよう。デビューは、60年代中盤に発売されたバンジョーが得意のフォーク・シンガー、ディック・ワイズマンとの共演盤に違いない。つまりヤングは、フォーク・シーンからデビューを飾ったのだった。 |
| ほとんど同時期に発売されたリチャード&ジムというフォーク・デュオのレコードにも顔を出している。彼らは、2枚のアルバムをキャピトルに残している。ヤングは、アコースティック・ギター伴奏者としてプロの道を歩め始めた。こうした背景からヤングは、60年代フォーク・リヴァイアヴァルの波をうけて、このなかで存在感を示そうと思ったようだ。アラバマからデンヴァーに流れ着き、この地のフォーク伝道者ハリー・タフト(デンヴァー・フォークロア・センターの主宰者)をワイズマンから紹介され、タフトのレコーディングにも参加したことがあった。が、フォークでは目が出なかった。最初の挫折だった。ヤングは、1968年RCAから発売された西海岸LAを拠点に活躍したサイケデリック・カントリー・ロック・バンド「ストーン・カントリー」にも足跡を残している。ヴァン・ダイク・パークスやステファン・スティルスなどと知り合い、刺激されて64年にバンドを立ち上げたというのだ。アルバムのプロデューサーは、ジェファーソン・エアプレインでお馴染みリック・ジャラードが務めた。ところがレコードは、ブレイクせずに終わってしまった。またまたの挫折だった。どうやらヤングは、フォークとカントリーという二つのジャンルでの成功を夢見て迷っていたようだ。 |
| アラバマで育ったヤングは、ご多分にもれず南部一帯で流行ったカントリーをいつも耳にしていた。ハンク・ウィリアムズ、ジョニー・ホートン、古き良き歌手ジミー・ロジャーズにも興味を示して。もちろんロックンロールの王者エルヴィス・プレスリーも大好きだった。ところが時代は、フォーク・ブームに傾け始めた。ヤングは、フォーク・リヴァイヴァルの重要な発信地、ニューヨーク・グリニッチ・ヴィレッジに向かった。コーヒー・ハウスに顔を出したりしたが、ボブ・ディランのパワーに自身を失ってしまった。そして逃げるようにLAに旅立った。先にふれたストーン・カントリー結成は、こうした流れから生まれた。 |
| 南部でカントリー歌手に憧れ、ニューヨークでフォークにのめり込み、LAで再びカントリー風味の音楽に惹かれ、というようにヤングは、目的が定まらない歌手として悩み生き延びてきた。試行錯誤は、彼の放浪癖にも原因があるようだ。69年、A&Mに録音のチャンスが与えられ、『Rock Salt & Nails』と表題されたアルバムが本作品だ。このアルバムは、こうしたヤングの悩みを内包したものだ。それだからこそ悲しみに満ち、切ないヴォーカルが際立っている。挫折を味わった男の哀愁が見事に表現されている。ヤングの胸のうちは、きっと「ディランになりたかった」「コマーシャル・カントリーには負けたくなかった」という想いがあふれていたに違いない。が、ここではそれを逆手にとった節が読み取れる。ヒット曲、スターといった言葉とは無縁だった男が、つらい旅路から得た「何か」を表現したかったのだろう。 |
| 本作の大きな話題は、ギター&ドブロにジェイムズ・バートン、ドラムスにハル・ブレイン、ジーン・クラークのマウスハープ(ハーモニカ)、グラム・パーソンズのオルガンといった錚々たるミュージシャンの参加だが、それよりもヤングの哀愁をおびたヴォーカル、全米各地を渡り歩いた経験から得たジャンルを飛び越えた傑作曲のカヴァーに注目したい。もちろん南部の土の香りが漂うもので、「スワンプ・ロック」として捉えてもよいだろう。ウディ・ガスリーやランブリング・ジャック・エリオットのうたう放浪ソング録音とは明らかに一線を画し、70年代ロック・シーンの幕開けに相応しい素晴らしいアメリカの心〜旅路を主題としたトラック作りとなった。 |
| スティーブ・ヤングは、フォーク・シーンからもカントリー・ロック・シーンからも見捨てられたが、結果的にはそれが良かった。マイナーなシンガー・ソングライターと呼ばれようが、ヤングのうた声はぼくたちが求める「男のロマン」が満ちあふれている。これは勝手な想い込みだが、本作の本質は「フォーク」だろう。このアルバム作りでもフォークのスーパー・スター、ボブ・ディランになり損ねた無念みたいなものが、そこはかとなく漂ってくる。そして挫折を味わった男の無情がうたわれている。この後、リプリーズから本作の延長といえる『Seven BridgesRoad』(MS-2081)、RCAからテキサス・カントリー歌手として再デビューを果たしアルバムをリリースするが、ロック・シーンでヤングが刻んだアルバムは一部音楽ファンには認められたものの、高い評価を得ることができなかった。これからもスティーブ・ヤングは、「伝説のシンガー・ソングライター」と呼ばれて行くに違いない。きっとそれで良いのだと思う。 |
| 01. That's How Strong My Love Is 目を見張らせるカヴァー。黒人音楽の頂点にたどり着いた男、オーティス・レディングの1964年作品を高鳴る感動を抑えながらしっとりとうたっている。グラム・パーソンズの地味なオルガン・フォローも要チェックだろう。 |
| 02. Rock Salt & Nails バートンの優雅なドブロがイントロから静かに聴こえ、アメリカ最後の放浪歌手として知られるユタ・フィリップスの作品カヴァーを、孤独なホ−ボーマンの姿を想い浮かべながらのきっとうたったのだろう。こころにしみる名唱だ。 |
| 03. I'm One Woman Man 50年代コロンビア・カントリーを代表するジョニー・ホートンのヒット・カヴァー。ホートンは、「シンギング・フィッシャーマン」というほど釣り好きで有名だった。ビック・ヒットは、この他に「ホンキー・トンク・マン」が広く知られている。 |
| 04. Coyote 60年代フォーク・リヴァイヴァルで一躍脚光を浴びたインディアンの血を引くシンガー・ソングライター、ピーター・ラ・ファージの作品カヴァー。ディランやフィル・オックスなどのプロテスト・ソングに強く影響され、自然保護を訴えたフォーク作品として知られている。 |
| 05. Gonna Find Me a Bluebird ハンク・ウィリアムズを擁したMGMレコードで活躍したカントリー歌手マーヴィン・レインウォーターのヒット・カヴァー。失恋ソングのようだ。「フォーキーなカントリー」といった佇まいがたまらない。 |
| 06. Love In My Time やっと自作曲が登場だ。イントロには60年代フォークを象徴するアコースティック・ギターが登場。そして徐々にゴスペル・コーラス、ストリングスなどを加えて盛り上げていく。スワンプ風情の匂いを発散させる傑作。「永遠(とわ)の愛」をうたったものだ。 |
| 07. Seven Bridges Road ヤングの体験を活かした放浪ソング。アコースティック・ギターとストリングスの絡みがいっそうの哀愁感を漂わしている。素朴なヴォーカルが、ゆっくりと胸に迫ってくる。後にヤングの代表作となったのは、充分に頷けるものだ。 |
| 08. Kenny's Song ジミー・ロジャーズのあやしいヨーデルっぽヴォーカルがちょっぴり味わえる現代版放浪ソング。ケニー・オースティンという人物が書き上げたという。やはりこの男は、ギター弾き語りが良く似合う。後半にストリングスとドブロの掛け合い、といった仕掛けもなかなかだ。ヤングのドラマティックなヴォーカルは、ここでも真価を発揮。 |
| 09. Holler In The Swamp スワンプ・ロックが流行った折、曲名に「スワンプ」と記されているいることから、本盤を購入したファンも多かったという。じっとりと湿ったスワンプ特有のサウンドというより、ストリングスを配したニュー・フォークといえそうな作品。もちろんヤングが書き上げたものだ。 |
| 10. Hoboin' 汽車をタダ乗りして全米を放浪するホーボーは、白人だけの世界ではなかったようだ。黒人、中国人、そして何と日本人のホーボーも存在したというのだ。ここでは、黒人ブルース歌手ジョン・リー・フッカーがうたった放浪ソングを、ブルース歌手顔負けの泥臭いカヴァーでうたってくれる。 |
| 11. My Sweet Love Ain't Around ハンク・ウィリアムズは、カントリーの巨人という捉え方よりシンガー・ソングライターの系譜を辿るには外せない歌手として捉えるのがどうやら正解かも知れない。アルバム・ラストは、ウィリアムズのヒット・カヴァー。ザ・バーズ人脈のジーン・クラークのハーモニカもほど良い効果を発揮している。 |
| (1987年 / 2004年1月加筆) |
| 一覧に戻る | トップに戻る |